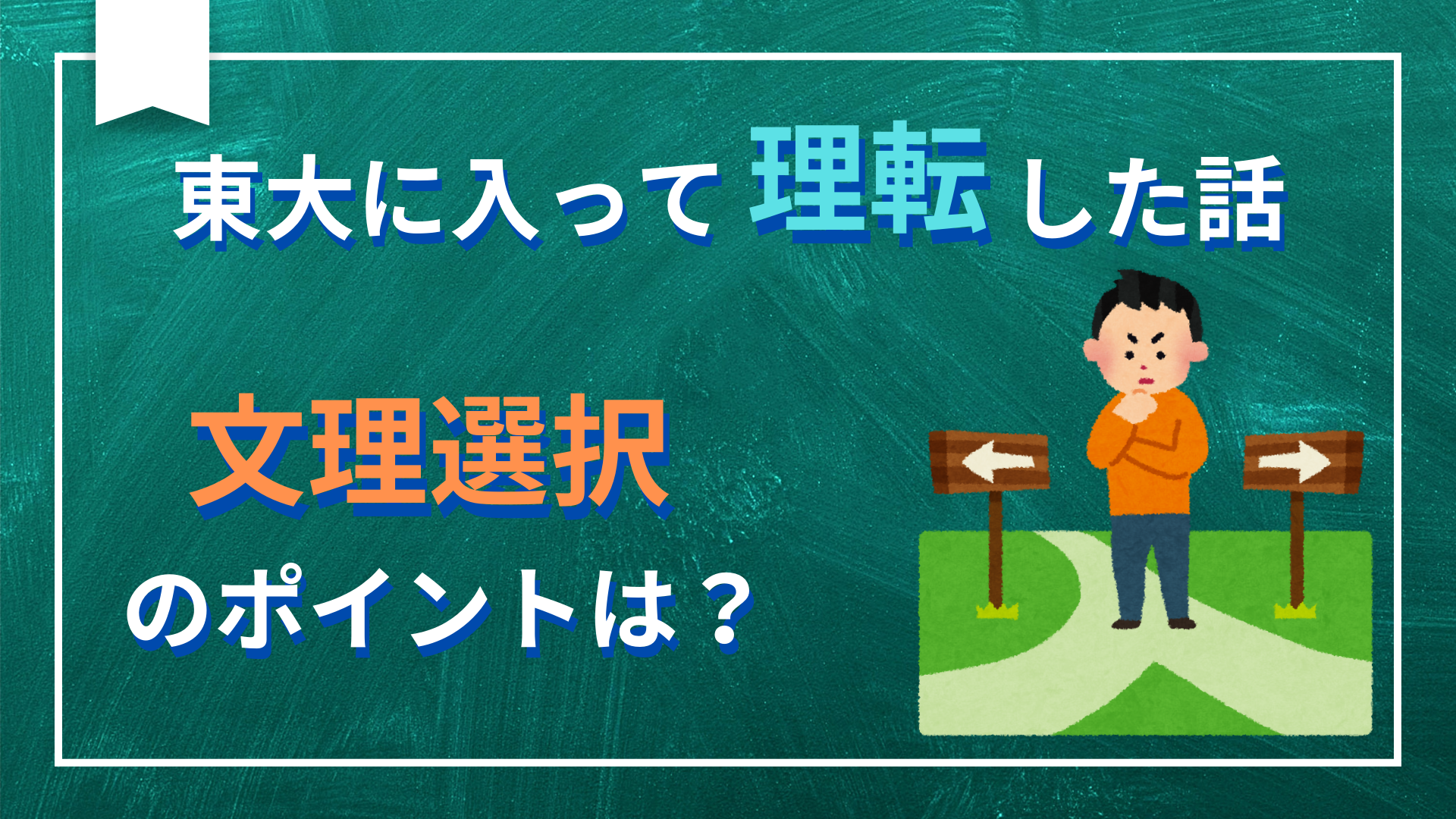
東大に入ってから理転した話 〜文理選択で何を考えていたか〜
クイズを読み込み中…
Loading...

0 /10
合計 0 いいね
ライターに応募
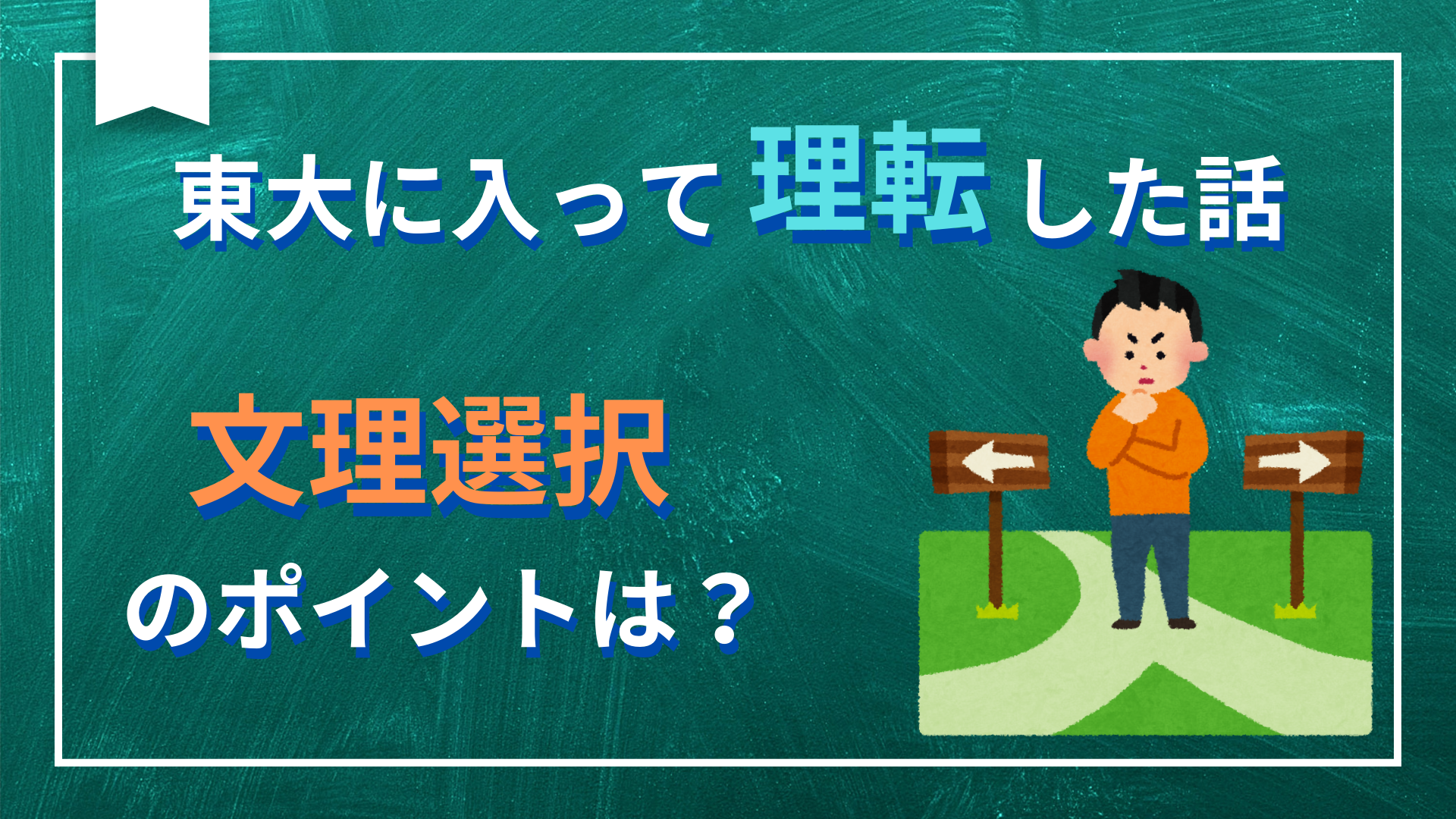


ずいしょうです!
私立中高一貫校から東京大学文科II類に入学。その後理転して現在は工学部に所属しています。
エンジニアをやっており、webサイトやアプリ、このメディアなど様々なシステムを開発しています!
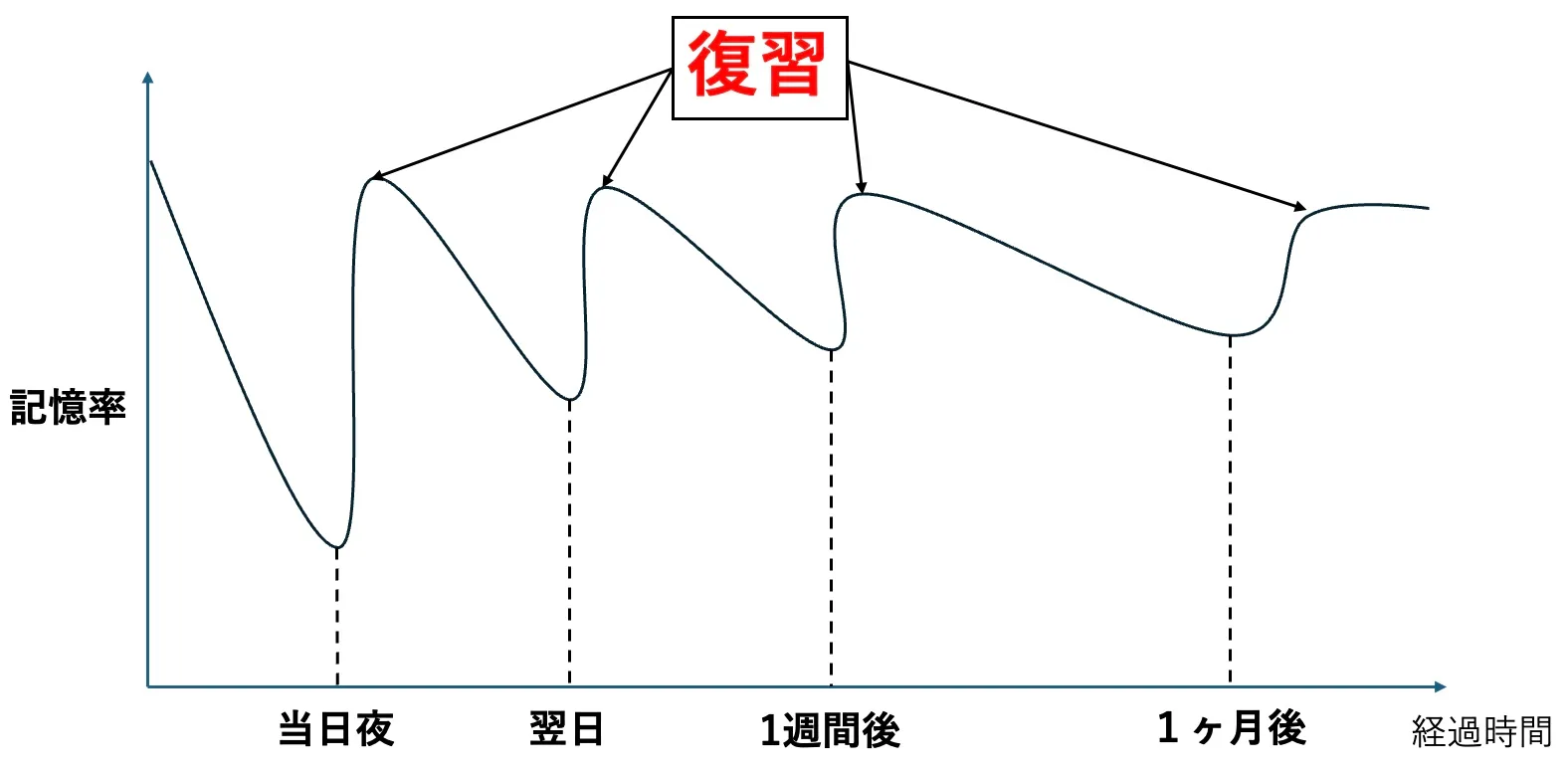
by むろ
2025年10月16日

by Ropi
2025年08月11日

by むろ
2025年08月18日

by かまだ
2025年10月02日

by むろ
2025年12月18日
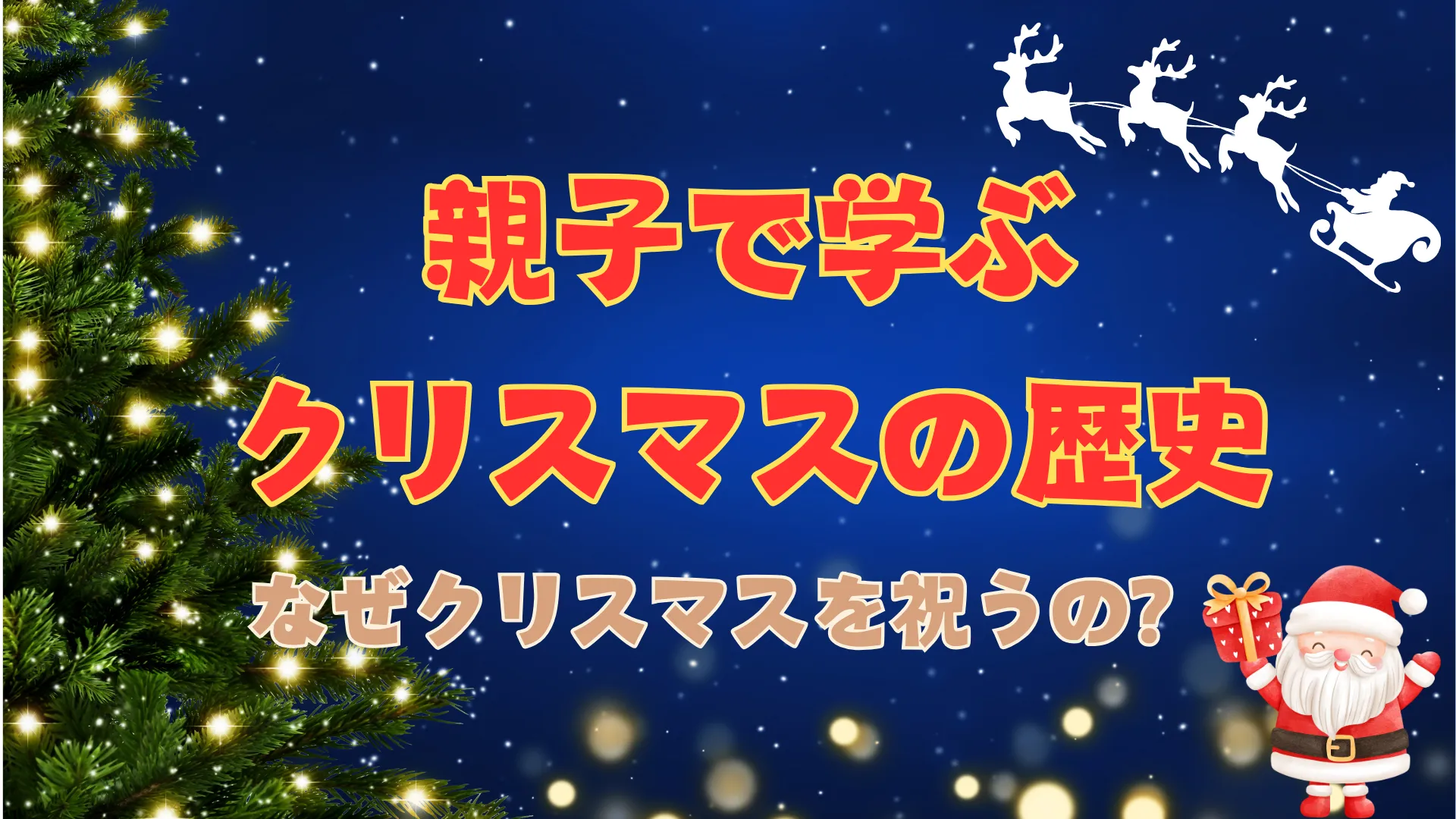
by ずいしょう
2024年12月24日

by かまだ
2024年12月30日

by えんざん
2025年01月02日

by takuma_ceo
2024年12月23日

by Ropi
2025年01月09日

by かまだ
2026年01月19日

by Ropi
2026年01月15日

by Ropi
2026年01月12日

by かまだ
2026年01月08日

by takuma_ceo
2026年01月05日