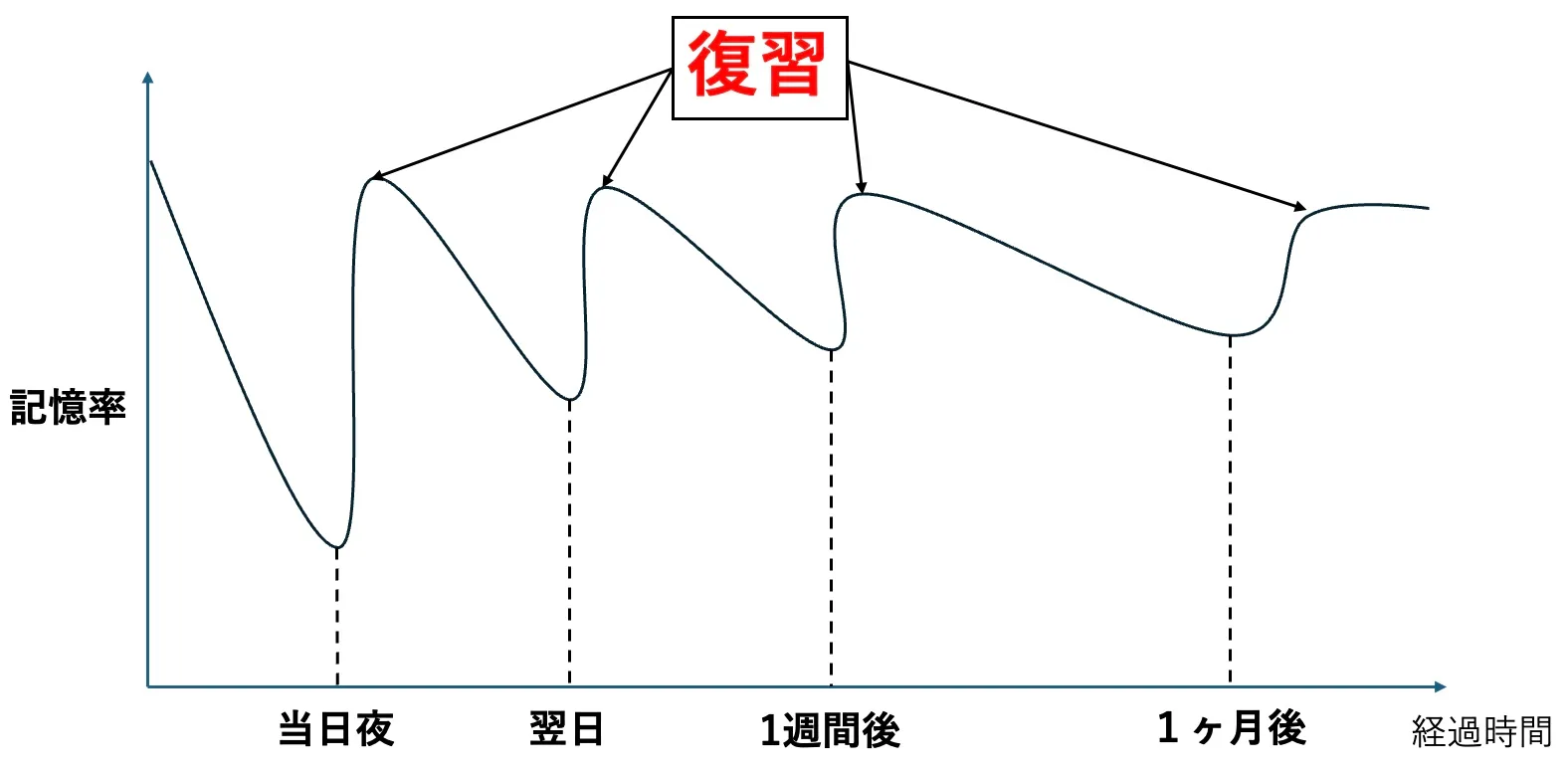
科学で解き明かす勉強法 ― 東大生が語る本当に効く学び方
クイズを読み込み中…
ハイスト勉強法記事シリーズ
シリーズ記事一覧Loading...

0 /10
合計 0 いいね
ライターに応募
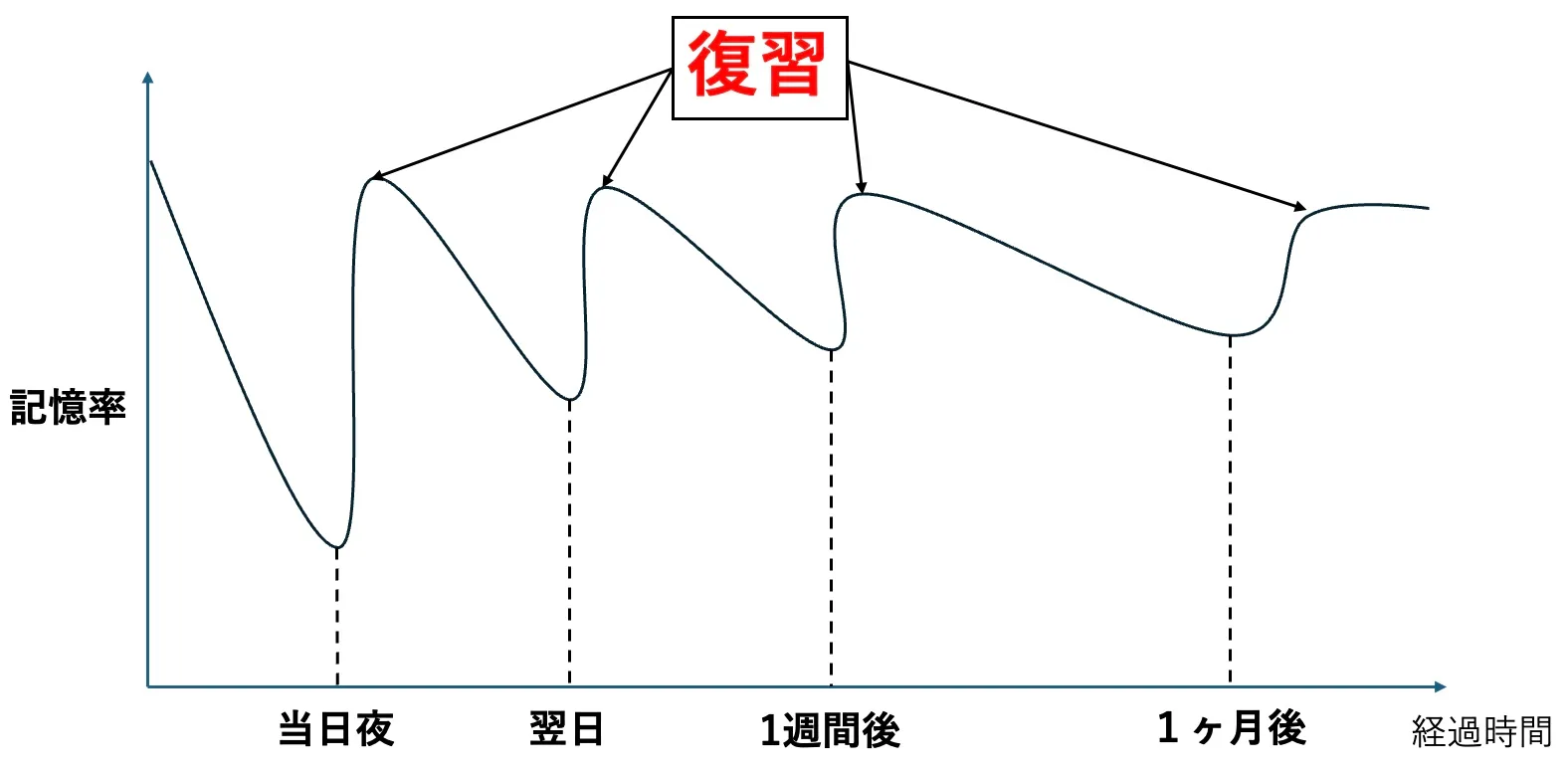
by むろ
2025年10月16日

by Ropi
2025年08月11日

by むろ
2025年08月18日

by かまだ
2025年10月02日

by むろ
2025年12月18日

by むろ
2025年11月27日

by むろ
2025年11月20日

by むろ
2025年08月21日

by Ropi
2025年08月11日

by かまだ
2025年10月02日

by むろ
2025年08月18日
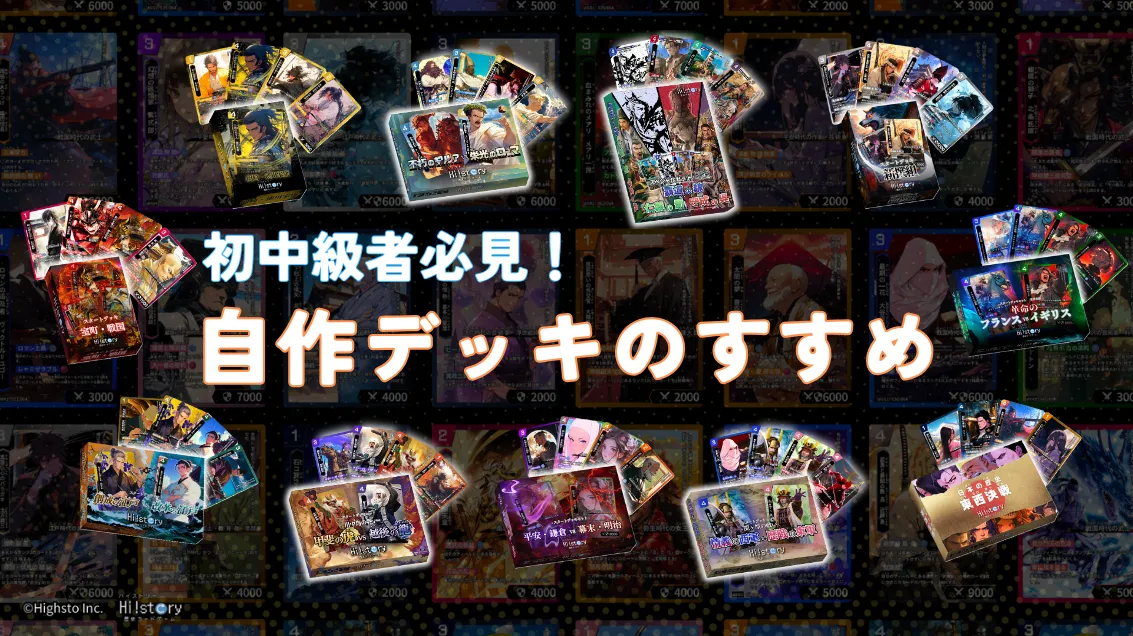
by かまだ
2025年09月08日

by むろ
2025年08月21日

by Ropi
2026年01月15日

by Ropi
2026年01月12日

by かまだ
2026年01月08日

by takuma_ceo
2026年01月05日

by かまだ
2025年12月25日