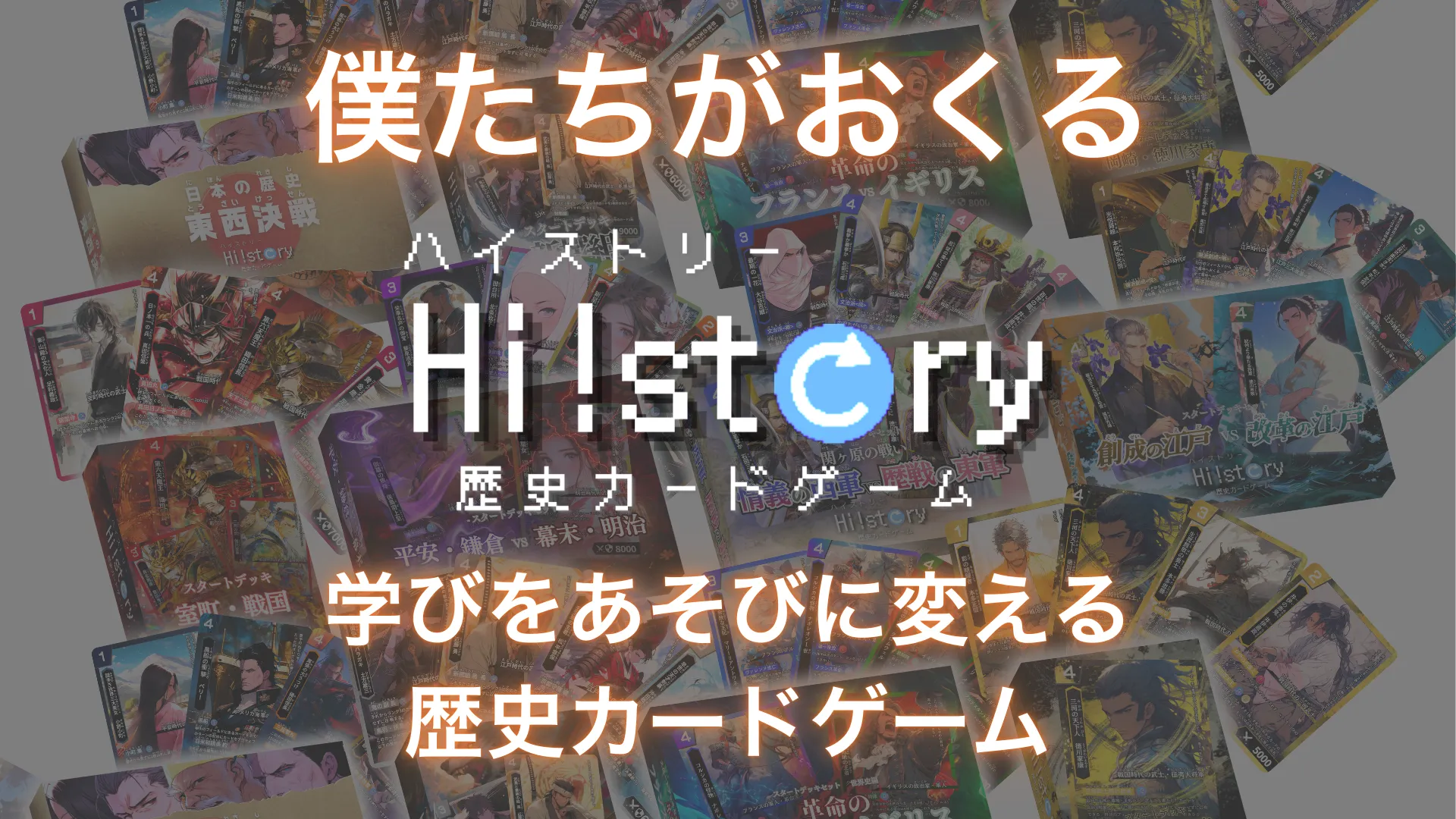【後編】灘中に受かるまでの軌跡|6年生の過ごし方、過去問、合格発表の日
クイズを読み込み中…
ハイスト勉強法記事シリーズ
シリーズ記事一覧Loading...

0 /10
合計 0 いいね
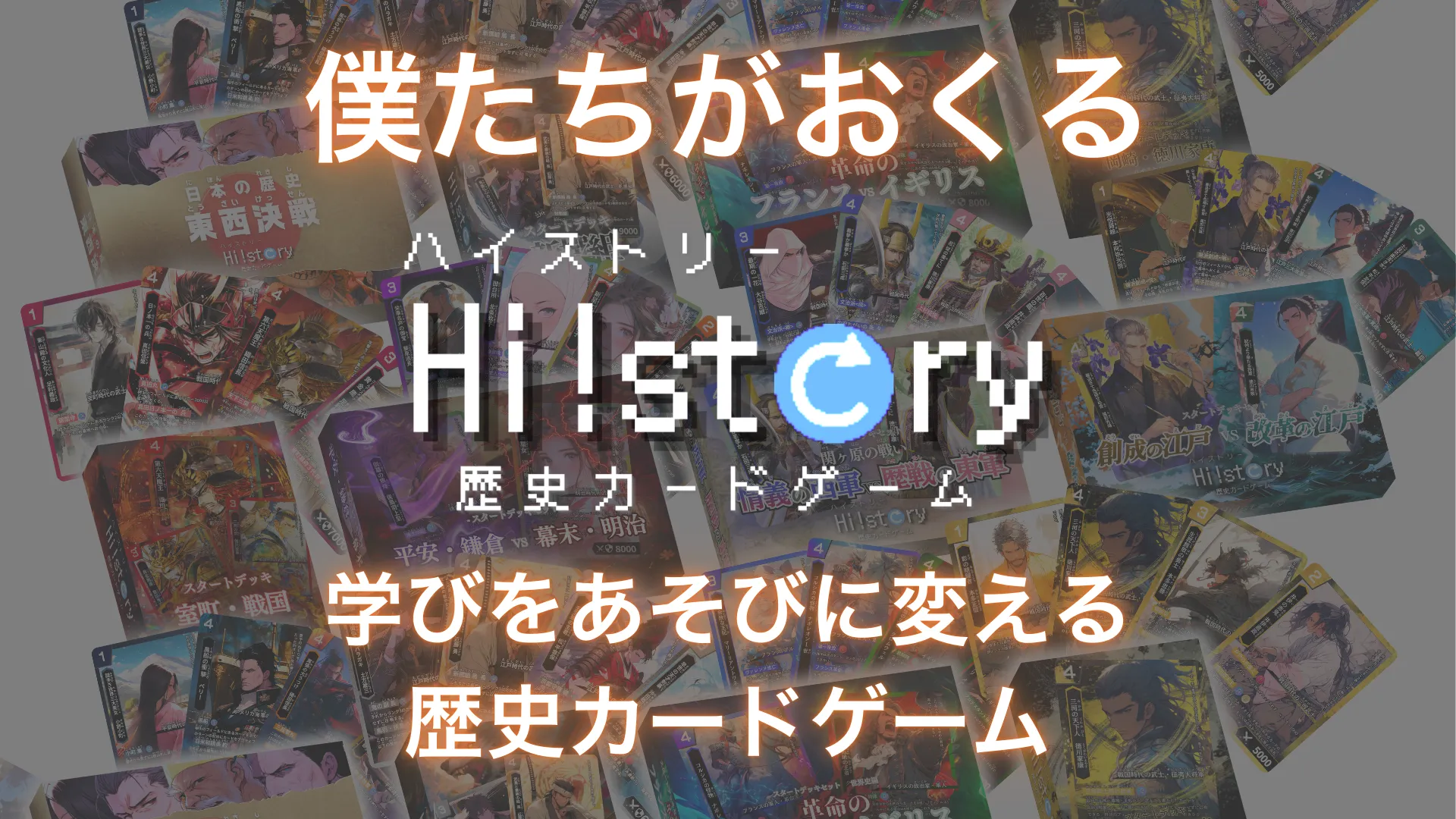



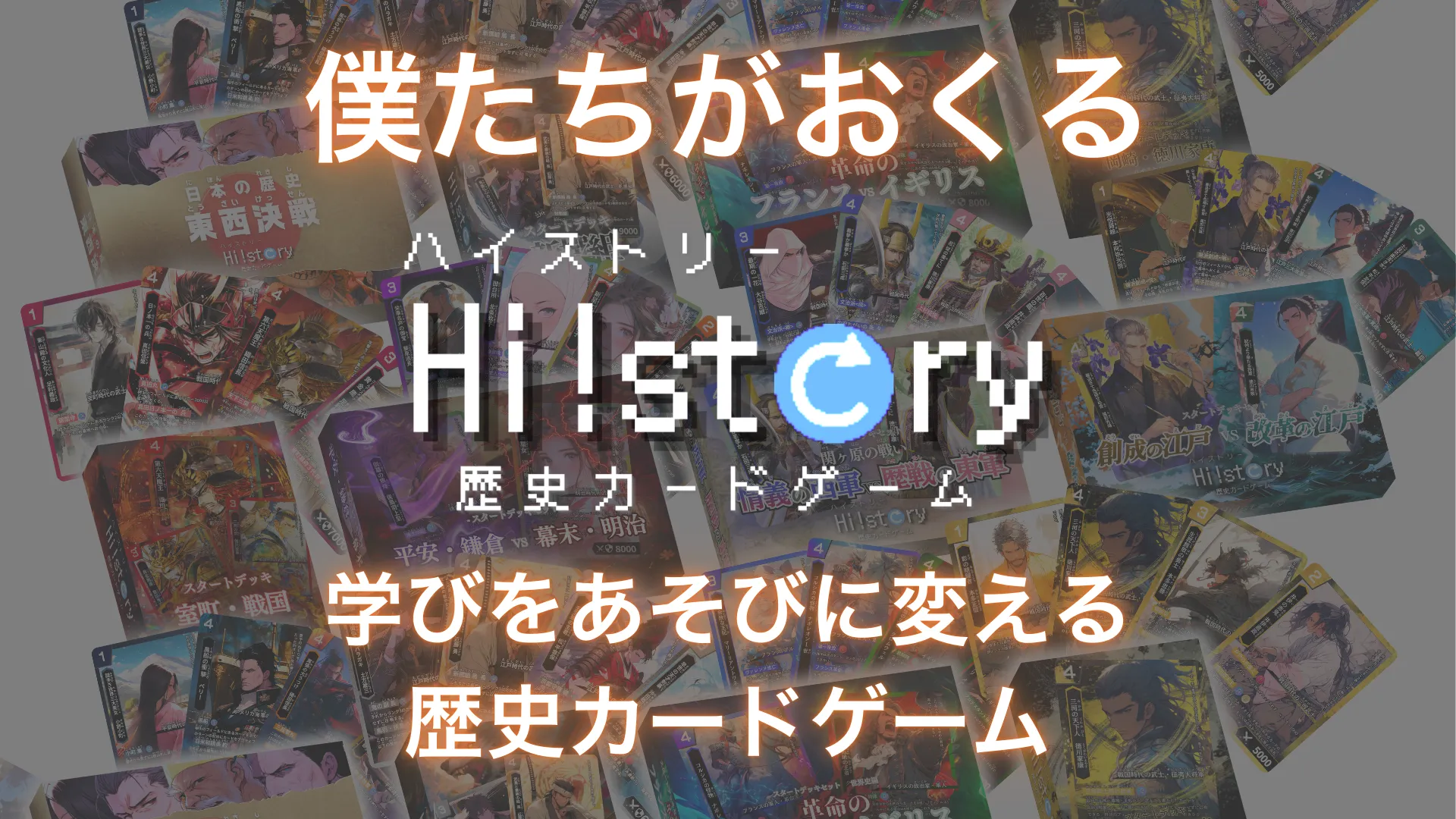

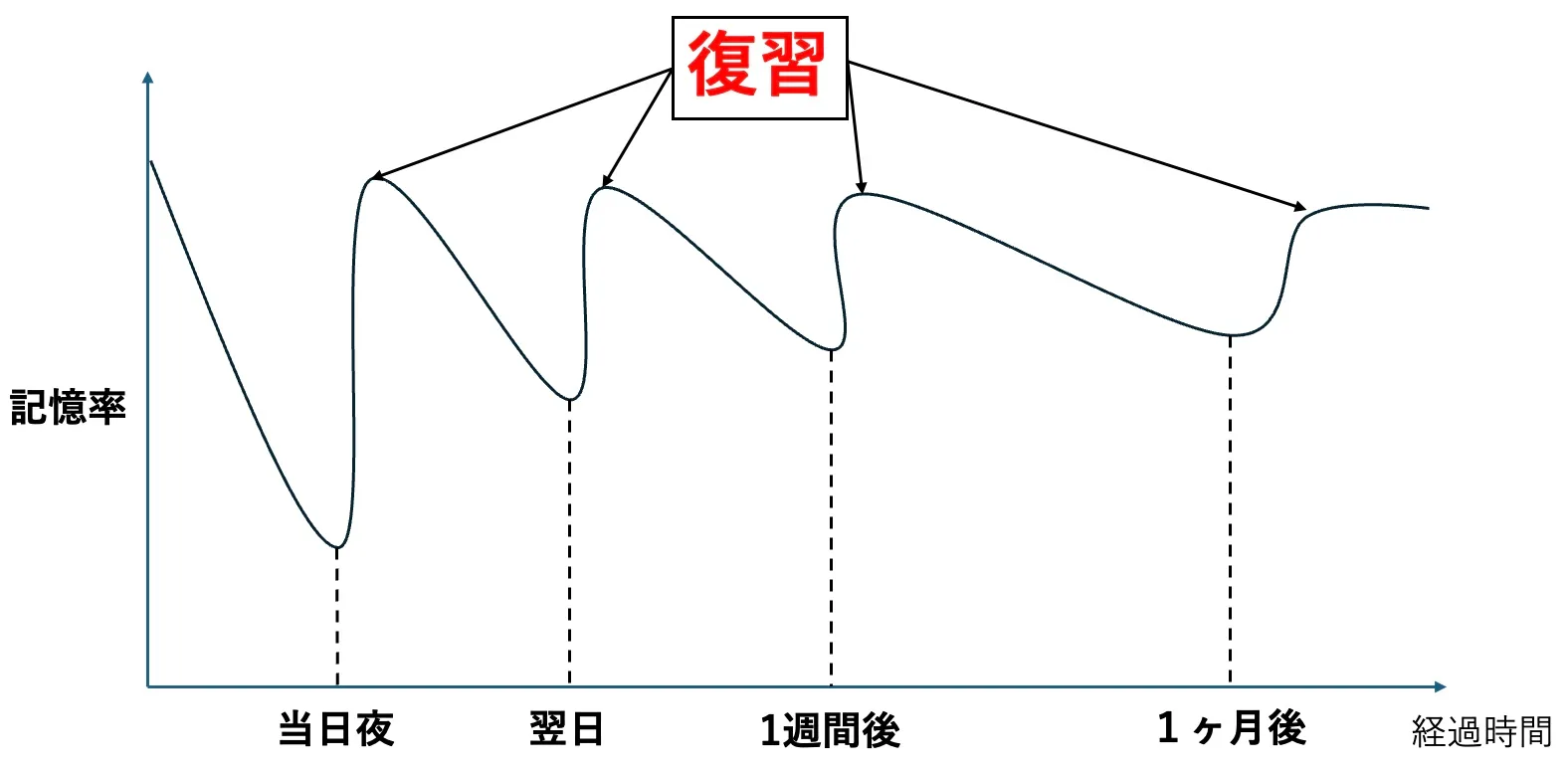
by むろ
2025年10月16日

by Ropi
2025年08月11日

by かまだ
2025年10月02日

by むろ
2025年08月18日

by むろ
2025年12月18日

by むろ
2026年02月09日

by むろ
2026年01月26日

by むろ
2025年11月27日

by むろ
2025年08月18日

by Ropi
2025年08月11日

by むろ
2025年07月17日
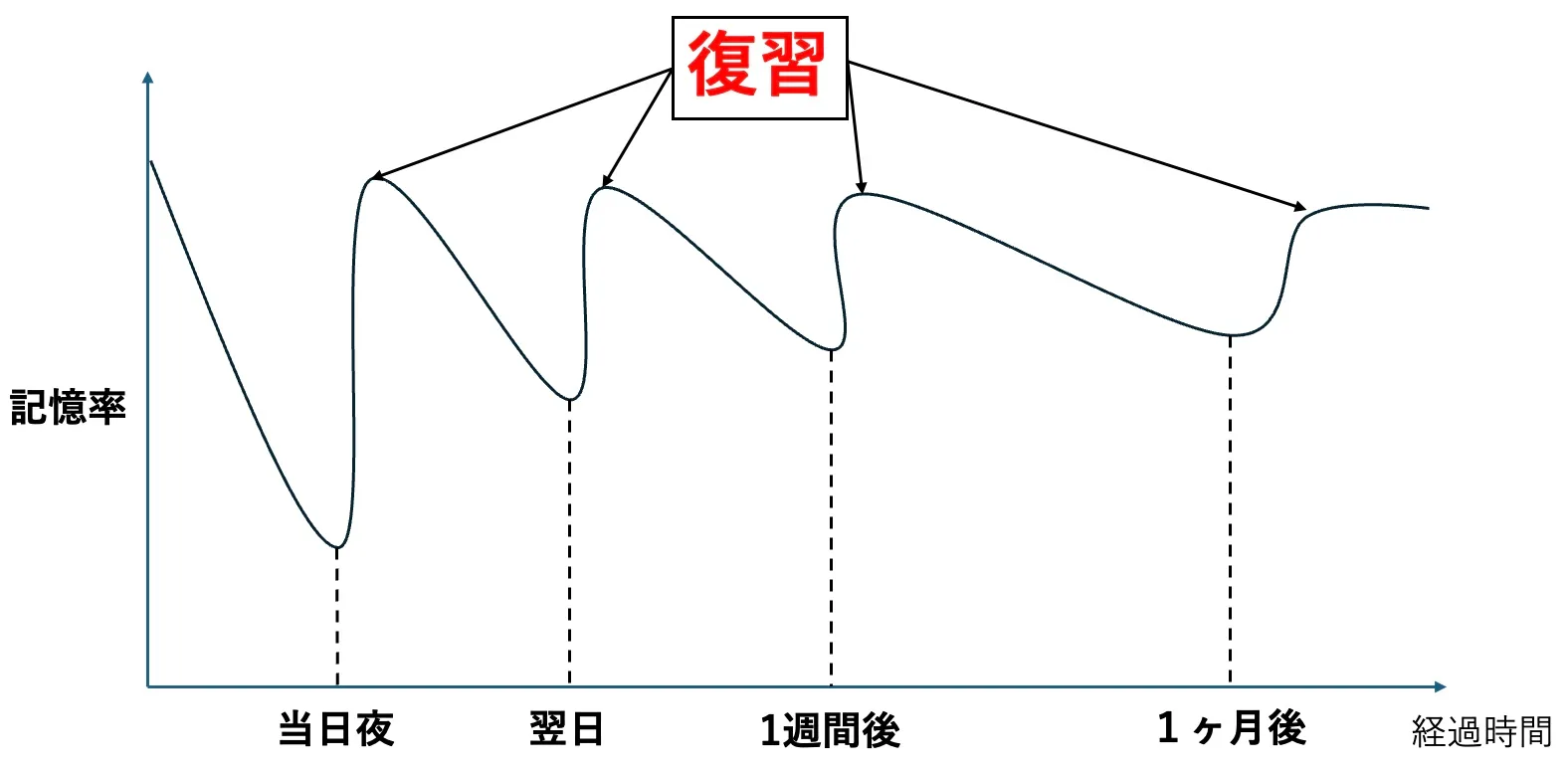
by むろ
2025年10月16日
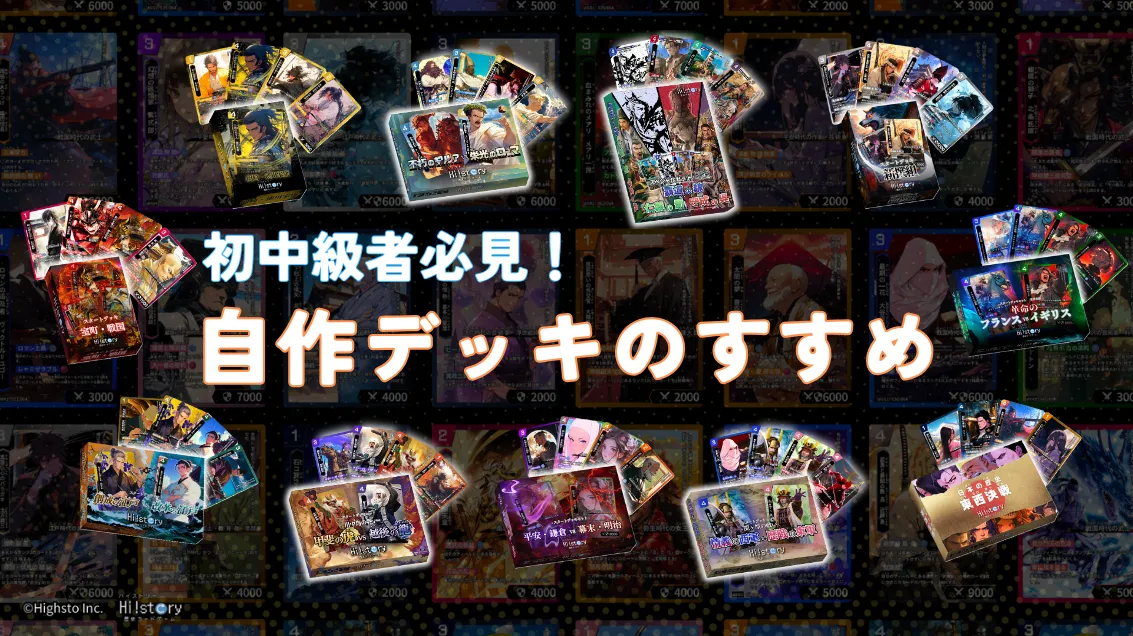
by かまだ
2025年09月08日

by かまだ
2026年02月19日
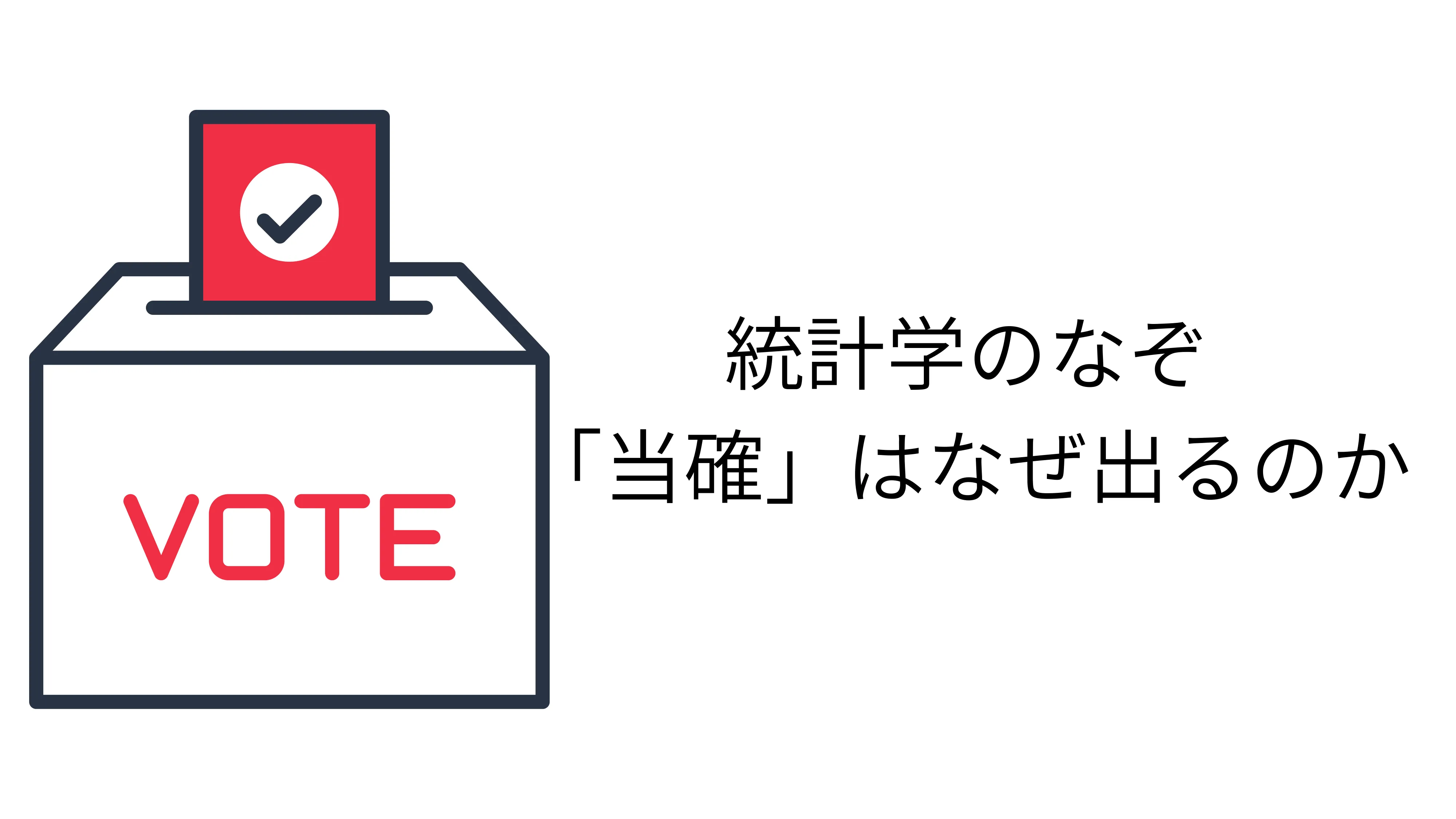
by Ropi
2026年02月16日

by かまだ
2026年02月12日

by かまだ
2026年02月05日
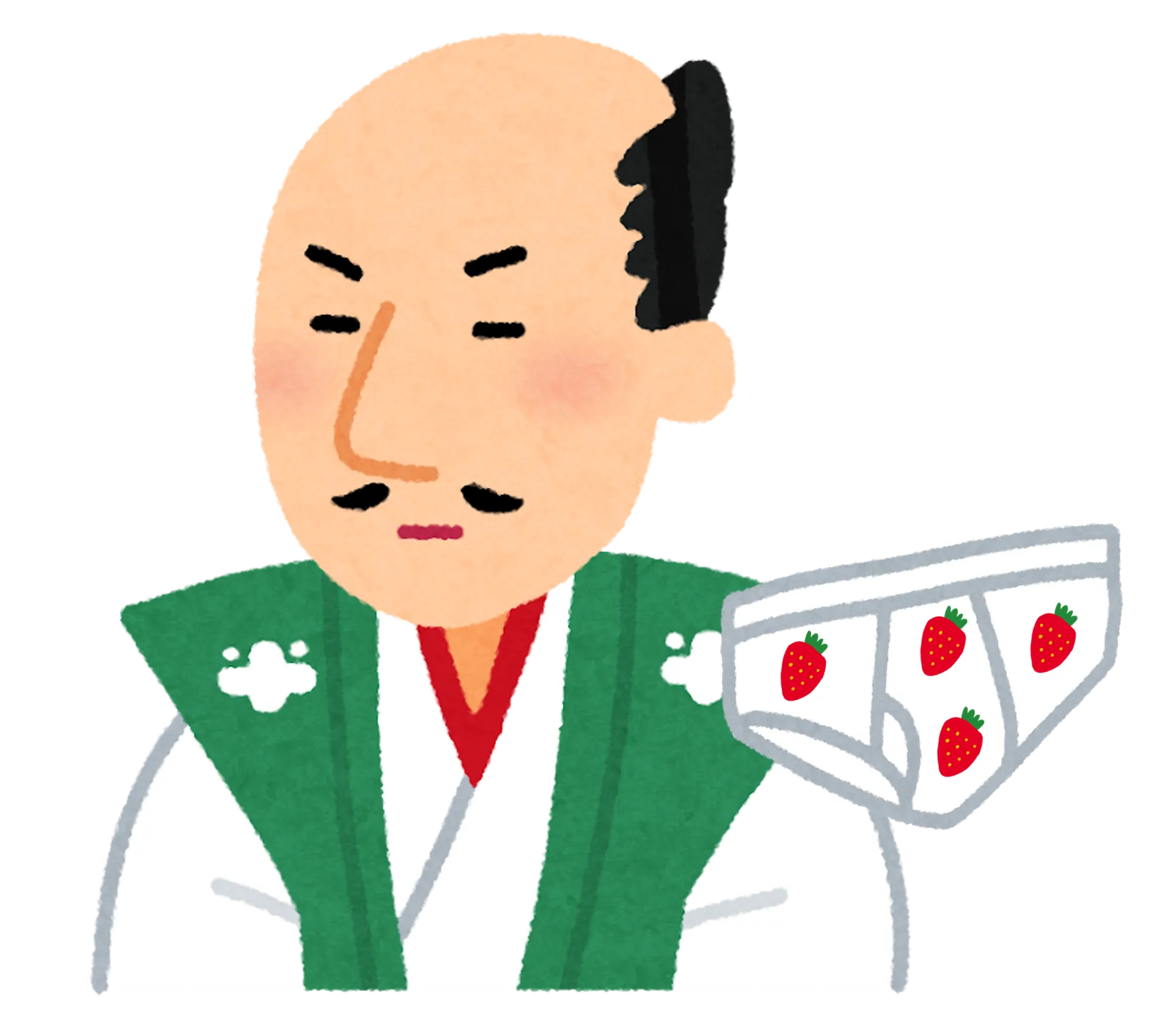
by かまだ
2026年02月02日