
【訪問記】江戸の守りの重要拠点・韮山反射炉
クイズを読み込み中…
Loading...

0 /10
合計 0 いいね
ライターに応募


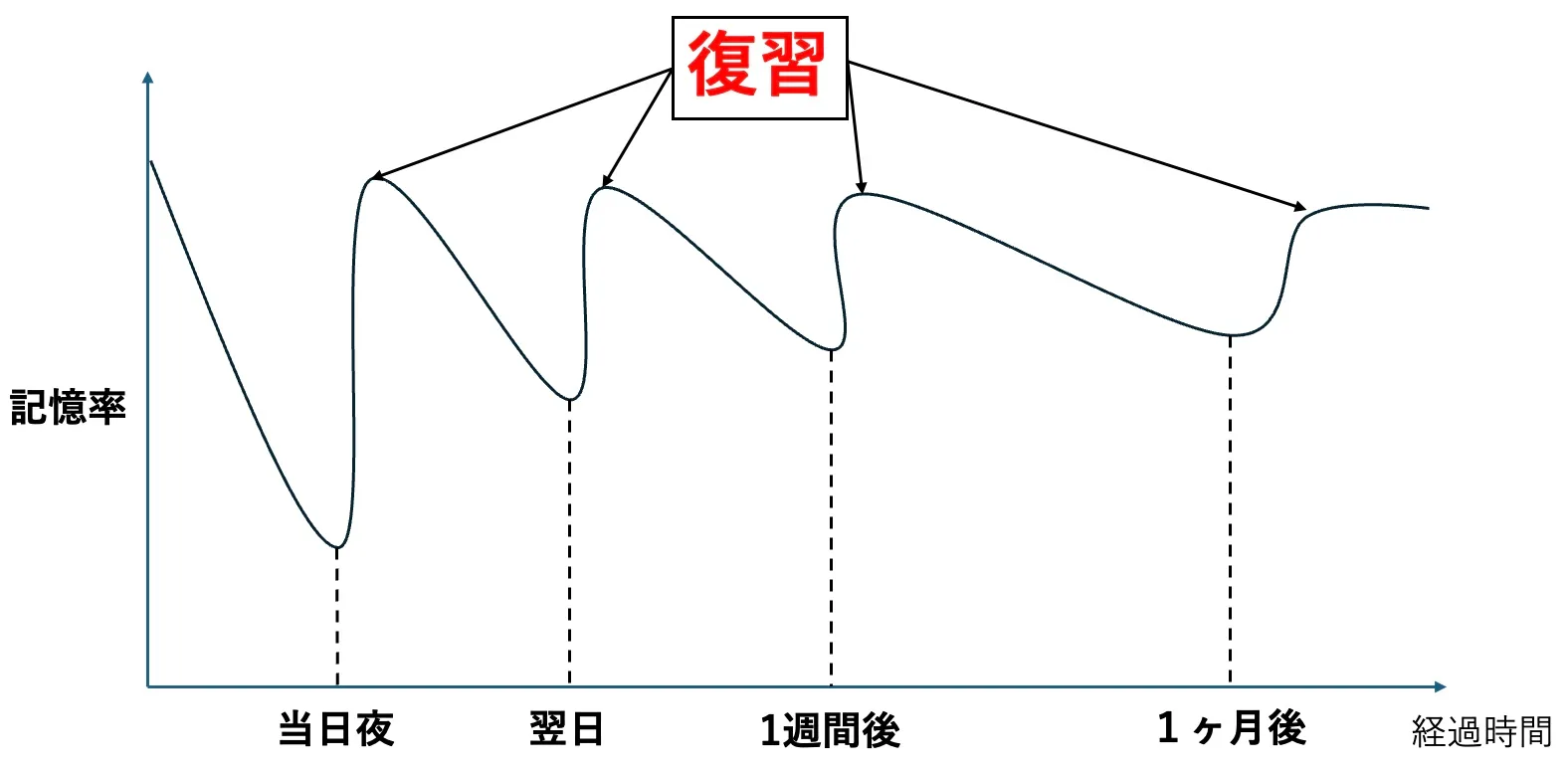
by むろ
2025年10月16日

by Ropi
2025年08月11日

by むろ
2025年08月18日

by かまだ
2025年10月02日

by むろ
2025年12月18日

by かまだ
2026年01月08日

by かまだ
2025年12月25日

by かまだ
2025年12月01日

by むろ
2025年08月18日

by Ropi
2025年08月11日

by むろ
2025年08月21日

by むろ
2025年07月17日
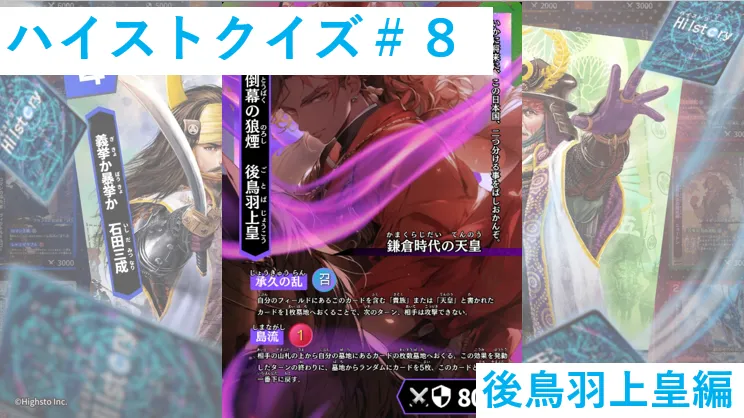
by かまだ
2025年08月14日

by Ropi
2026年01月15日

by Ropi
2026年01月12日

by takuma_ceo
2026年01月05日

by ノーサイドくらはし
2025年12月15日
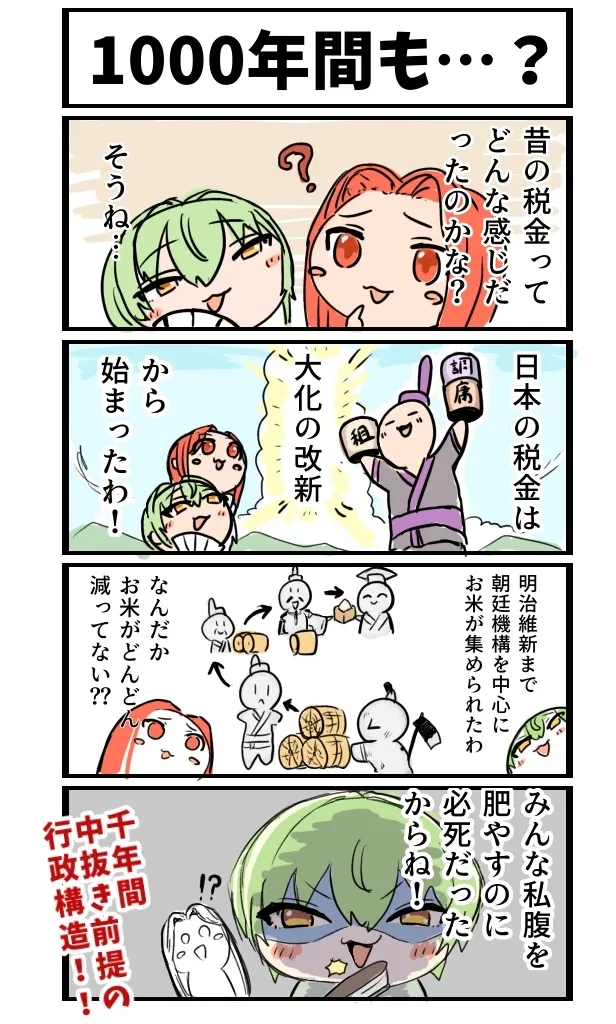
by ササノン制作班(ゆーき)
2025年12月04日