
「クマがかわいそう」は正しいか? 最新のニュースで思考力を鍛えよう【後編】
クイズを読み込み中…
Loading...

0 /10
合計 0 いいね
ライターに応募


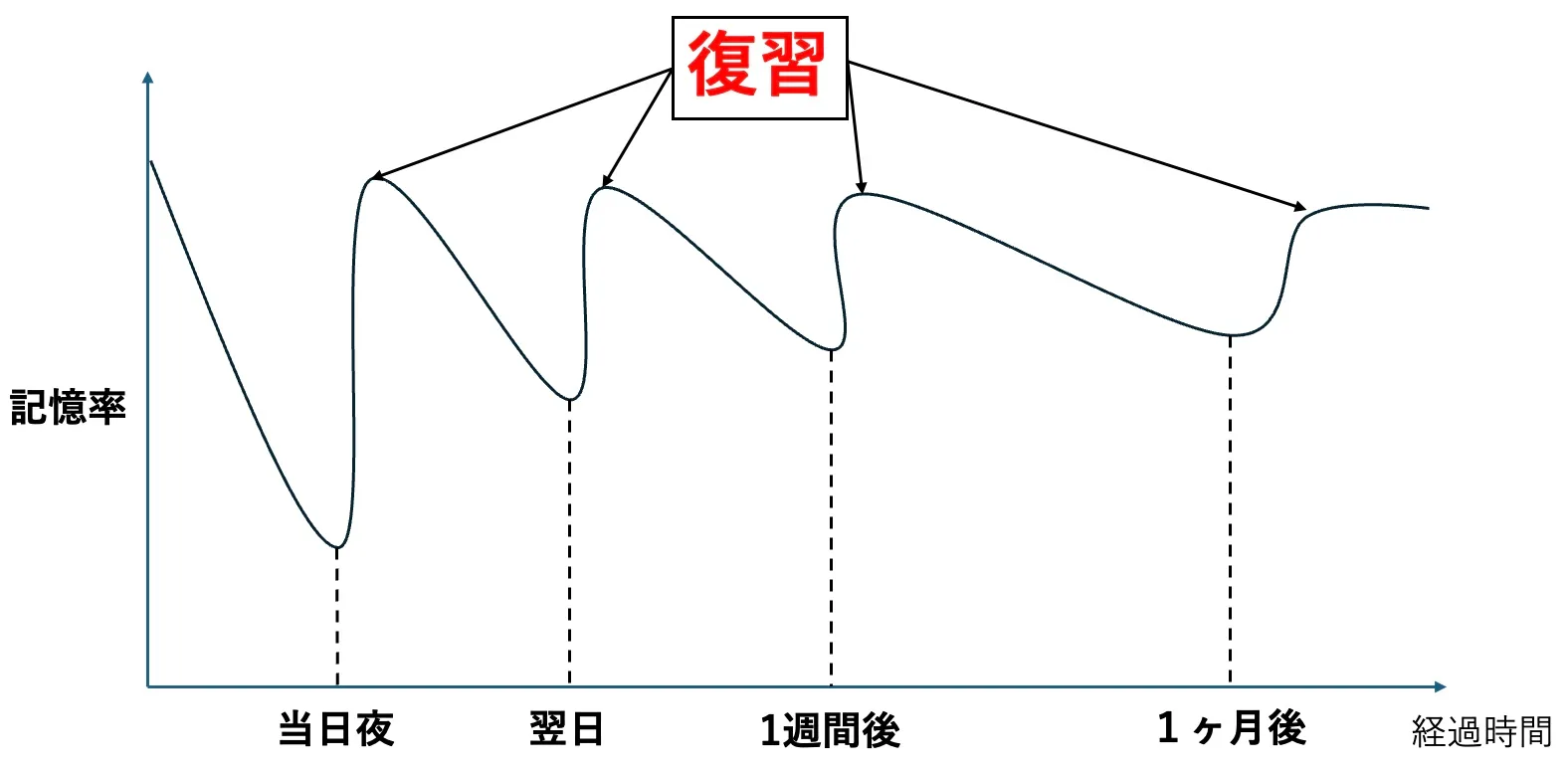
by むろ
2025年10月16日

by Ropi
2025年08月11日

by むろ
2025年08月18日

by かまだ
2025年10月02日

by むろ
2025年12月18日

by Ropi
2026年01月15日

by Ropi
2026年01月12日

by Ropi
2025年11月13日

by むろ
2025年08月18日

by Ropi
2025年08月11日

by むろ
2025年08月21日
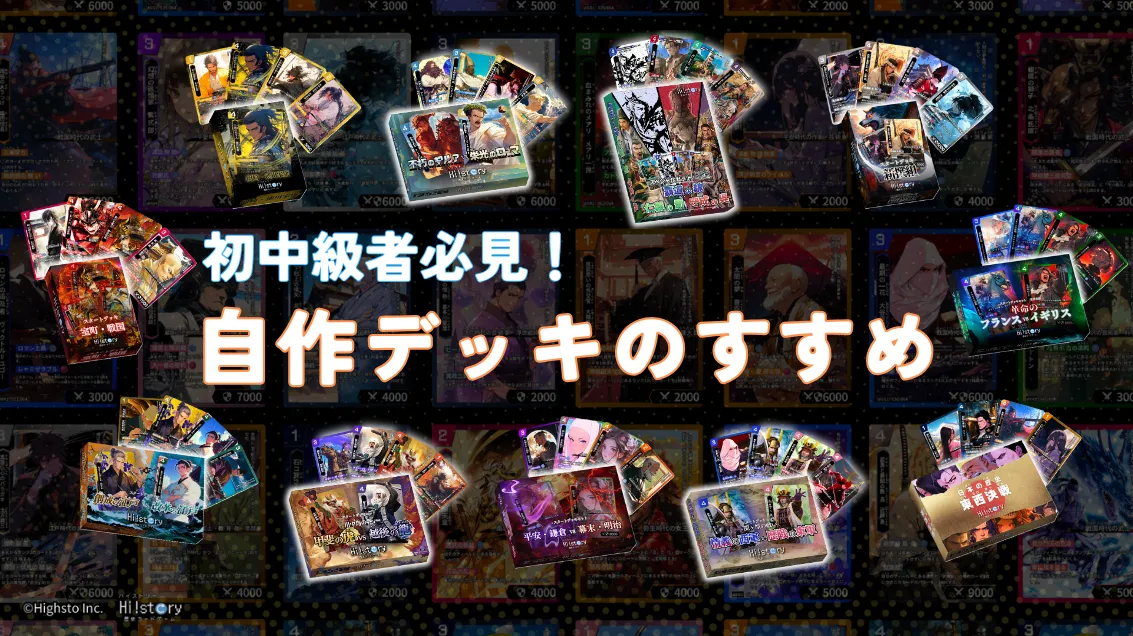
by かまだ
2025年09月08日

by むろ
2025年07月17日