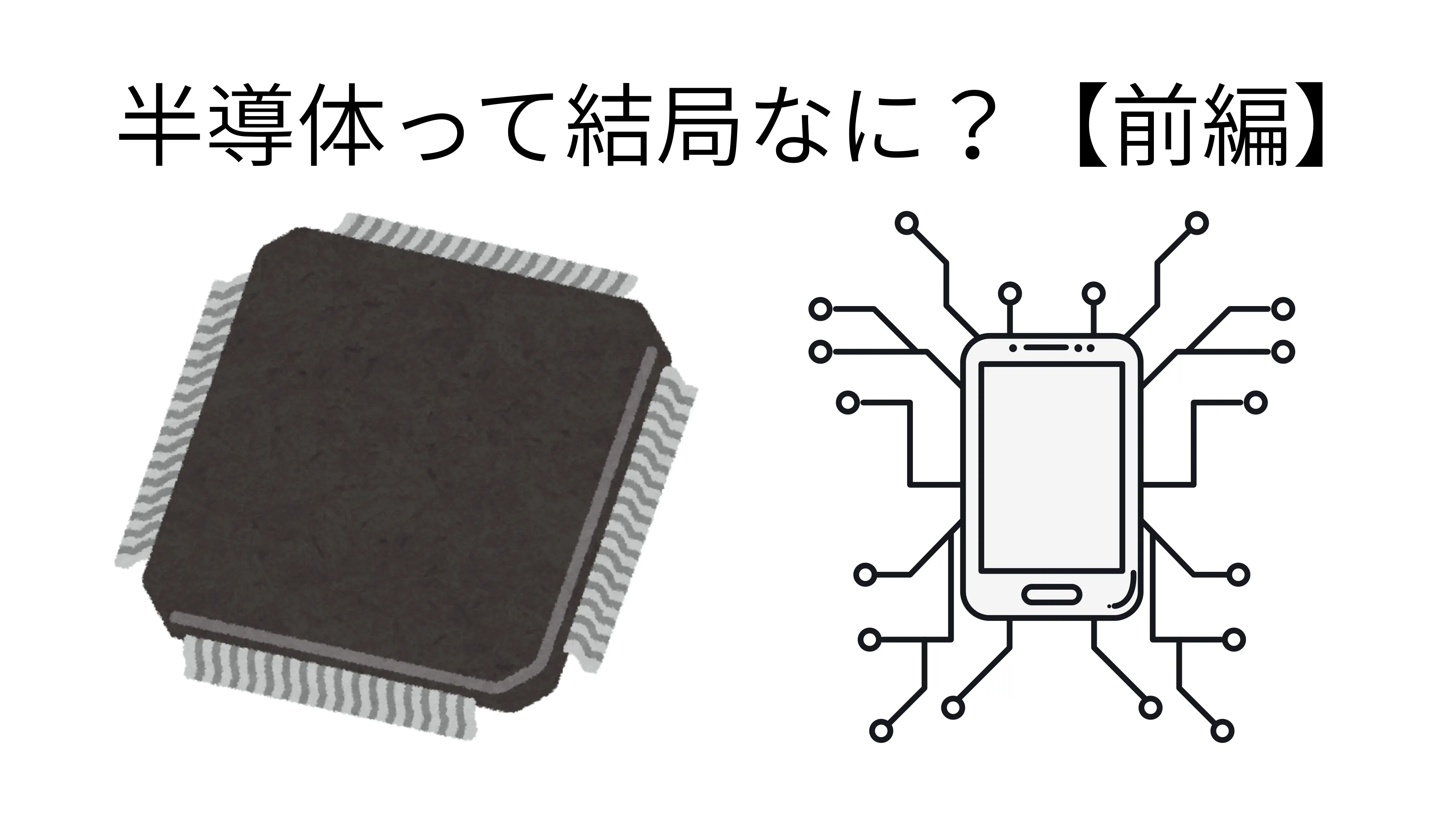
半導体って結局なに??? 小学生にもわかるガチ授業【前編】
クイズを読み込み中…
Loading...

0 /10
合計 0 いいね
ライターに応募
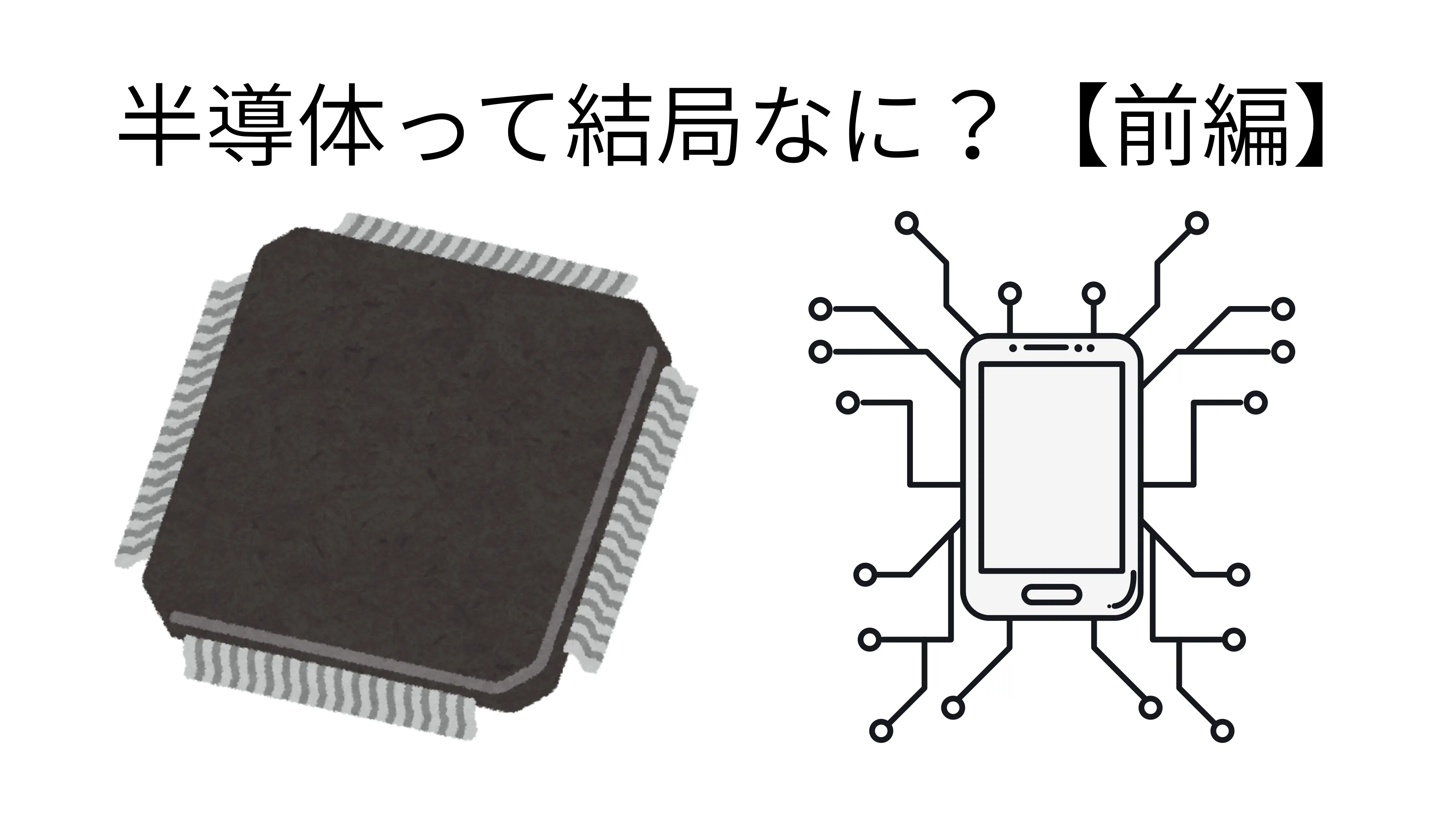

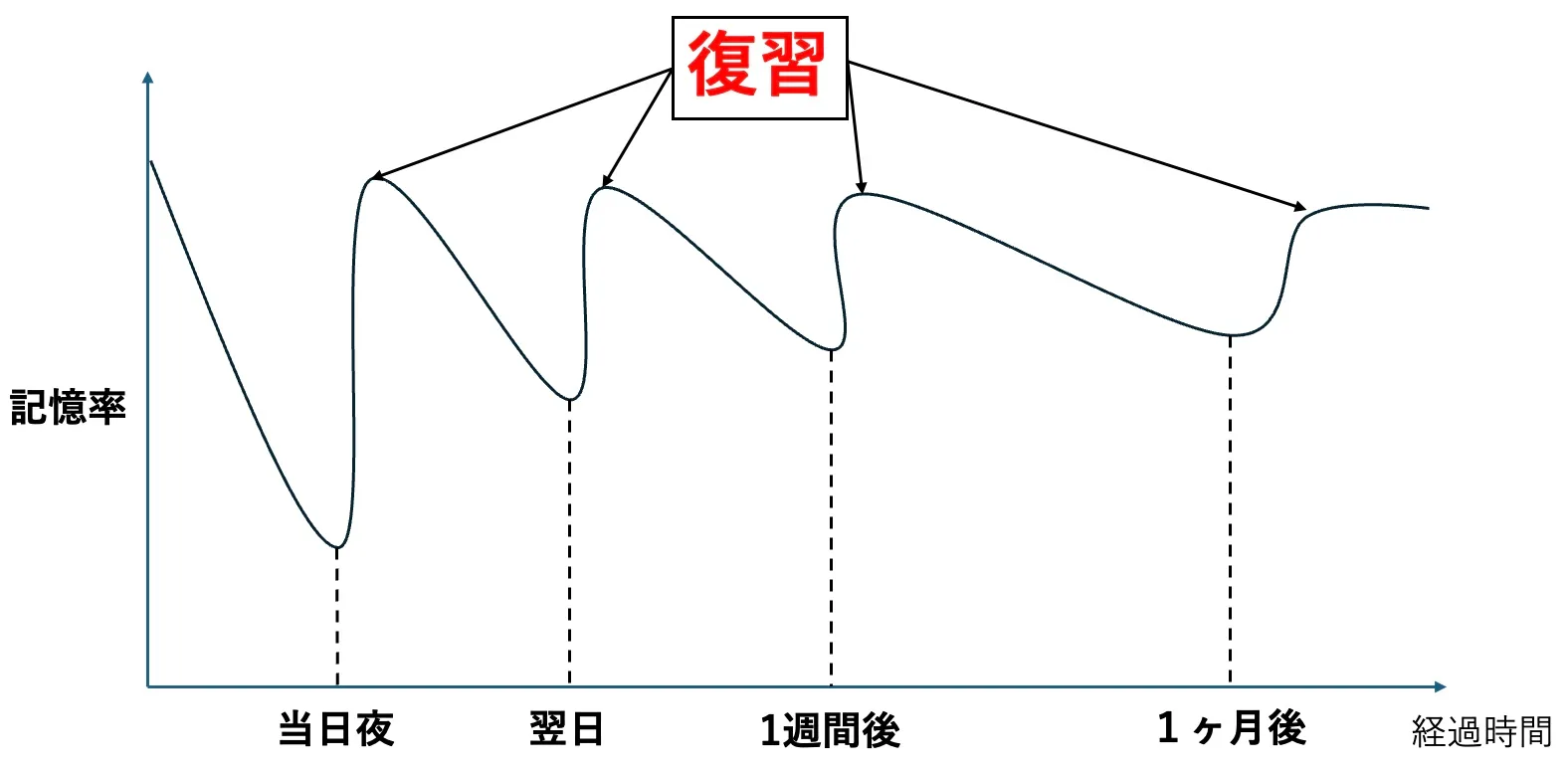
by むろ
2025年10月16日

by Ropi
2025年08月11日

by むろ
2025年08月18日

by かまだ
2025年10月02日

by むろ
2025年12月18日

by Ropi
2026年01月15日

by Ropi
2026年01月12日

by Ropi
2025年11月13日
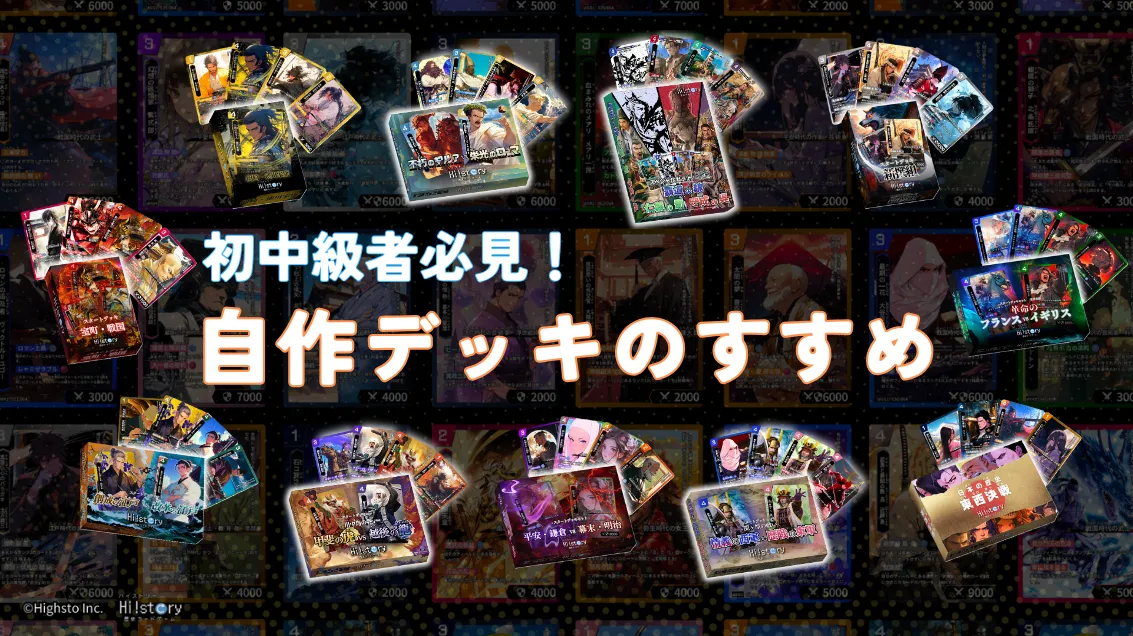
by かまだ
2025年09月08日

by むろ
2025年08月18日

by Ropi
2025年08月11日
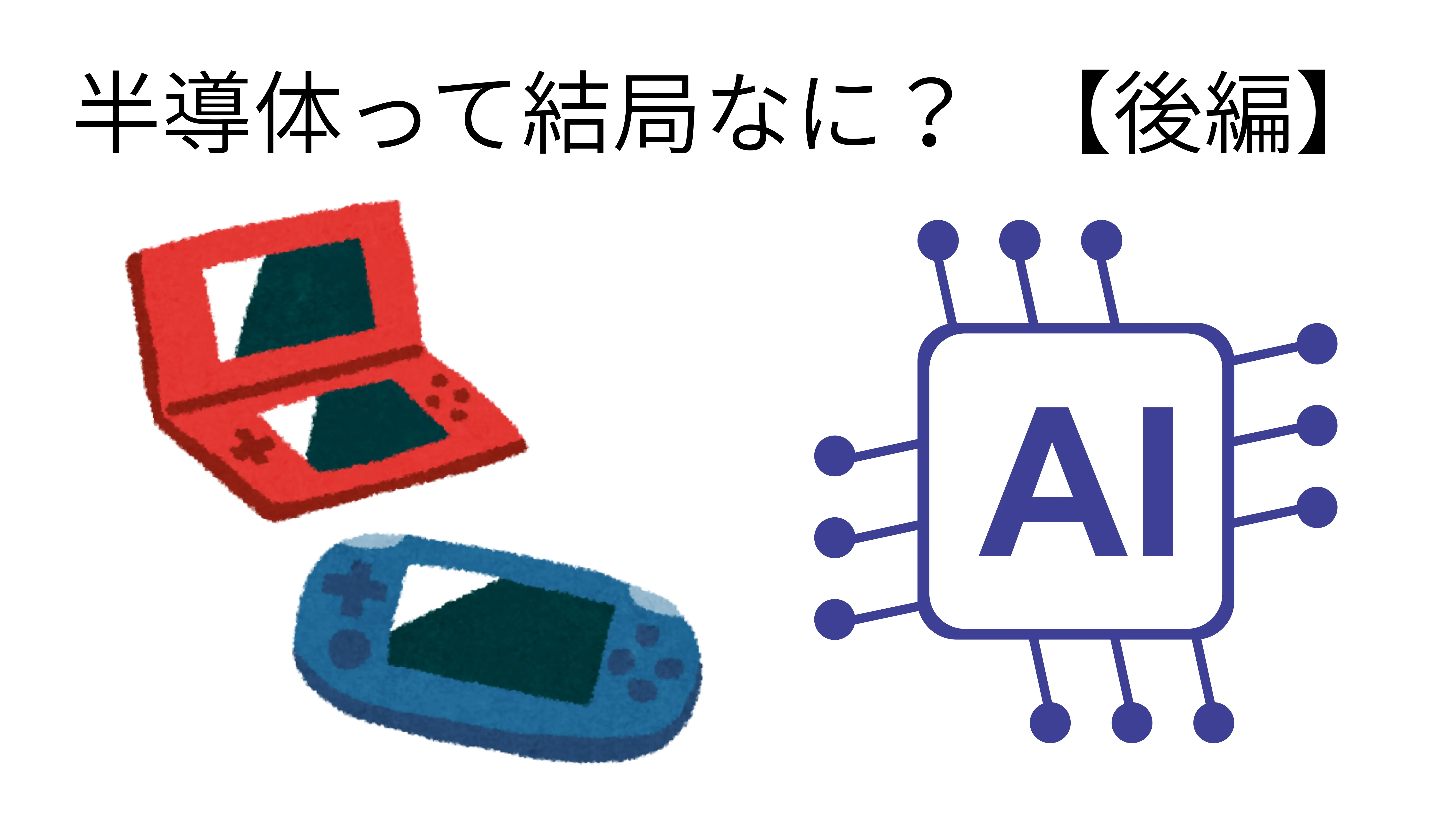
by Ropi
2025年09月18日

by むろ
2025年08月21日

by ササノン制作班(ゆーき)
2026年01月29日

by むろ
2026年01月26日
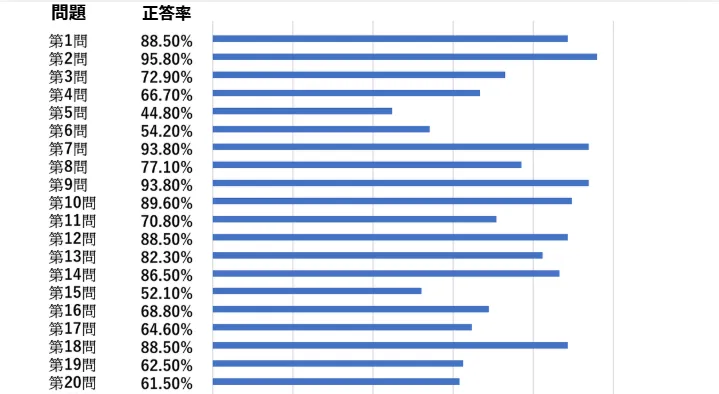
by かまだ
2026年01月22日

by かまだ
2026年01月19日

by かまだ
2026年01月08日