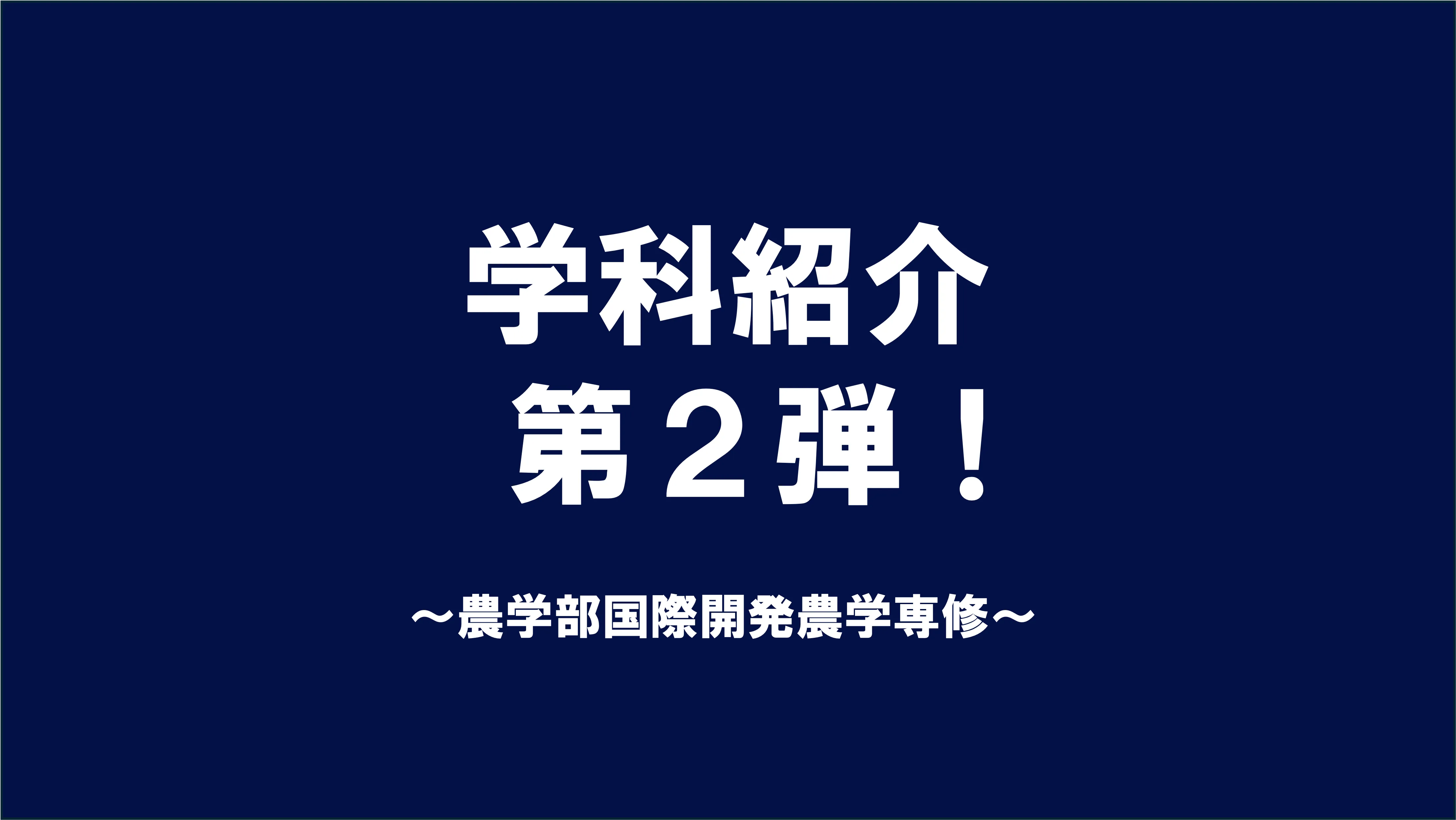
学科紹介 ~東大・農学部国際開発農学編~
クイズを読み込み中…
Loading...

0 /10
合計 0 いいね
ライターに応募
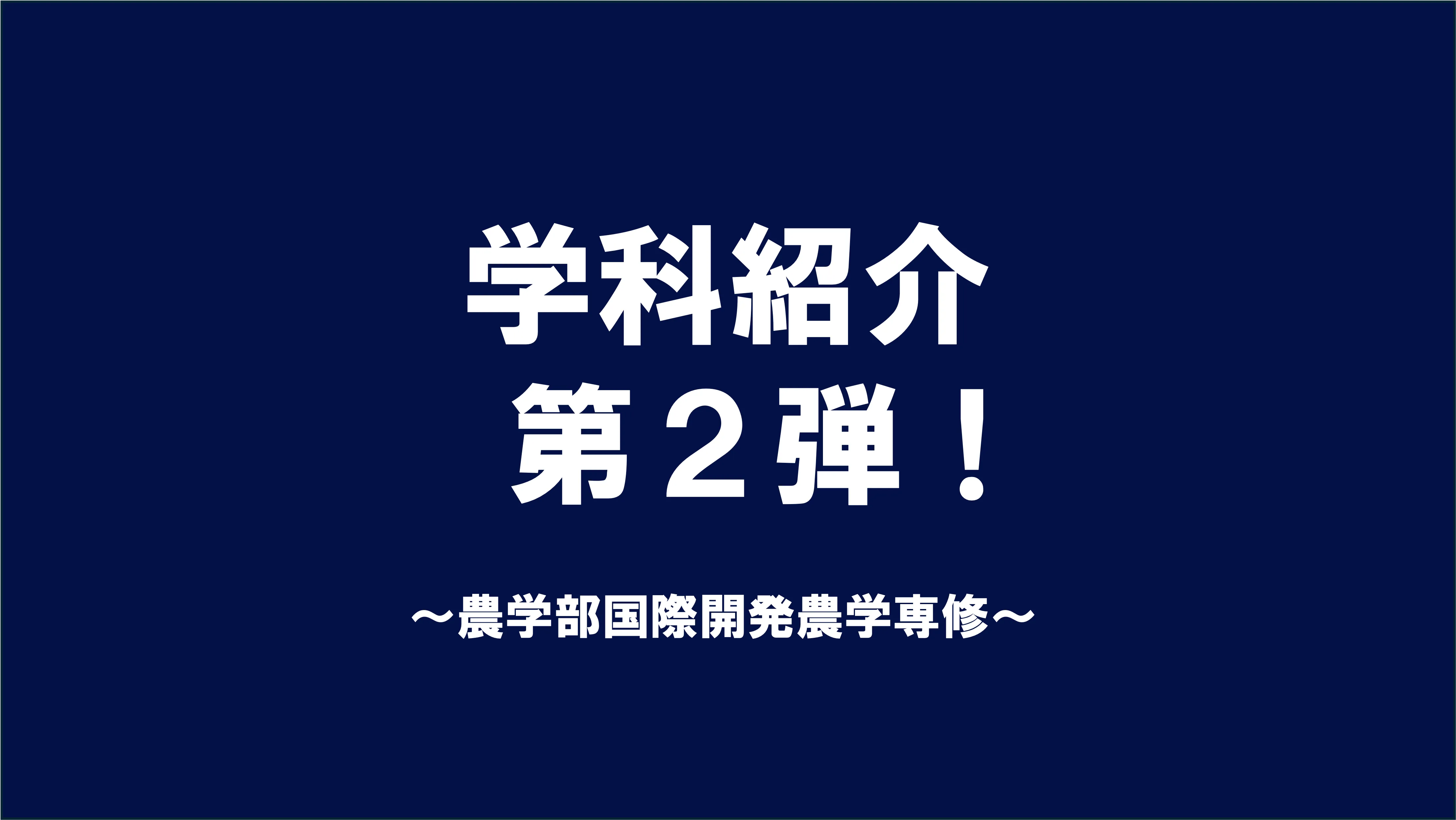

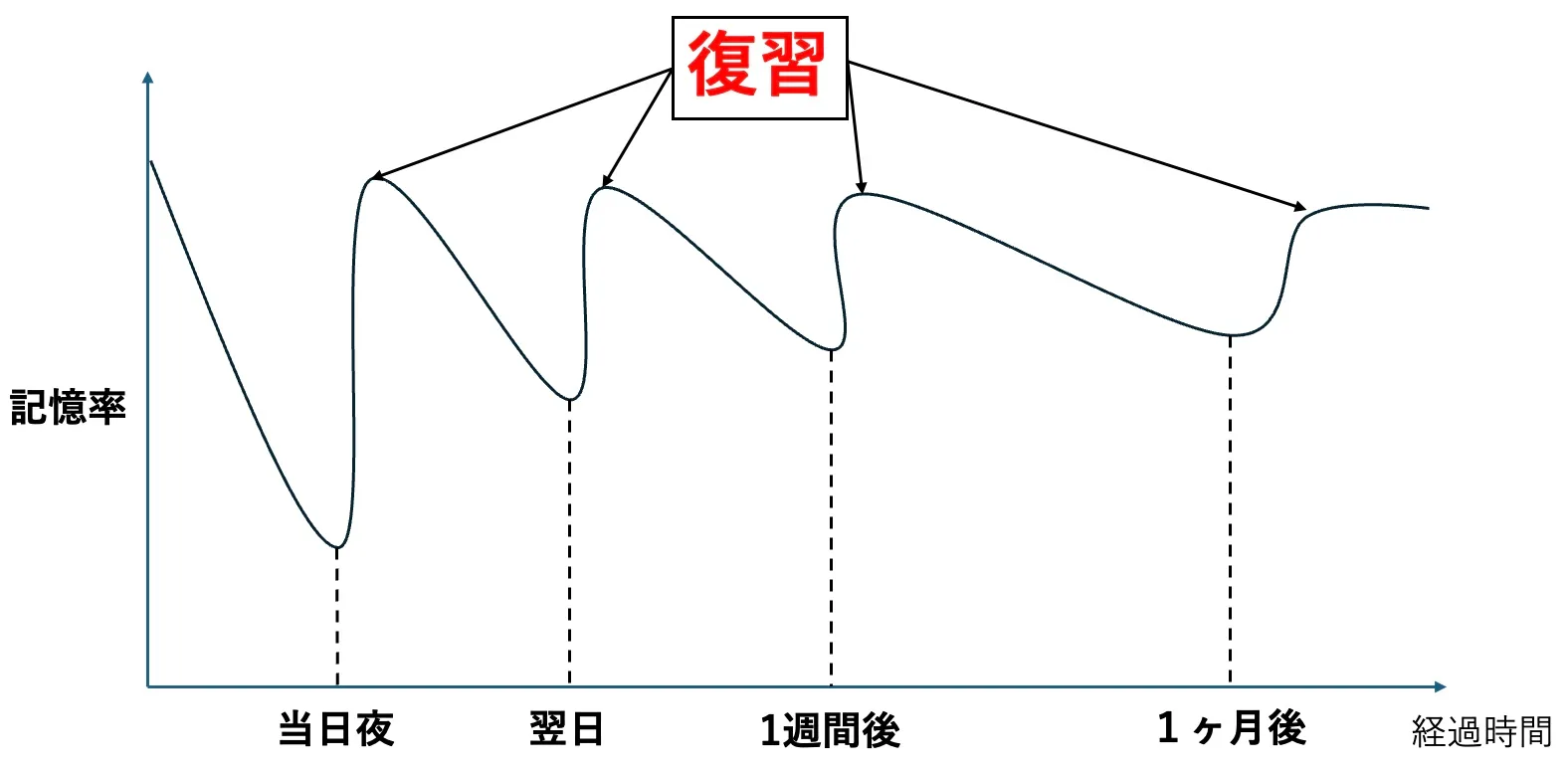
by むろ
2025年10月16日

by Ropi
2025年08月11日

by むろ
2025年08月18日

by かまだ
2025年10月02日

by むろ
2025年12月18日

by ノーサイドくらはし
2025年12月15日

by ノーサイドくらはし
2025年06月26日

by ノーサイドくらはし
2025年05月08日
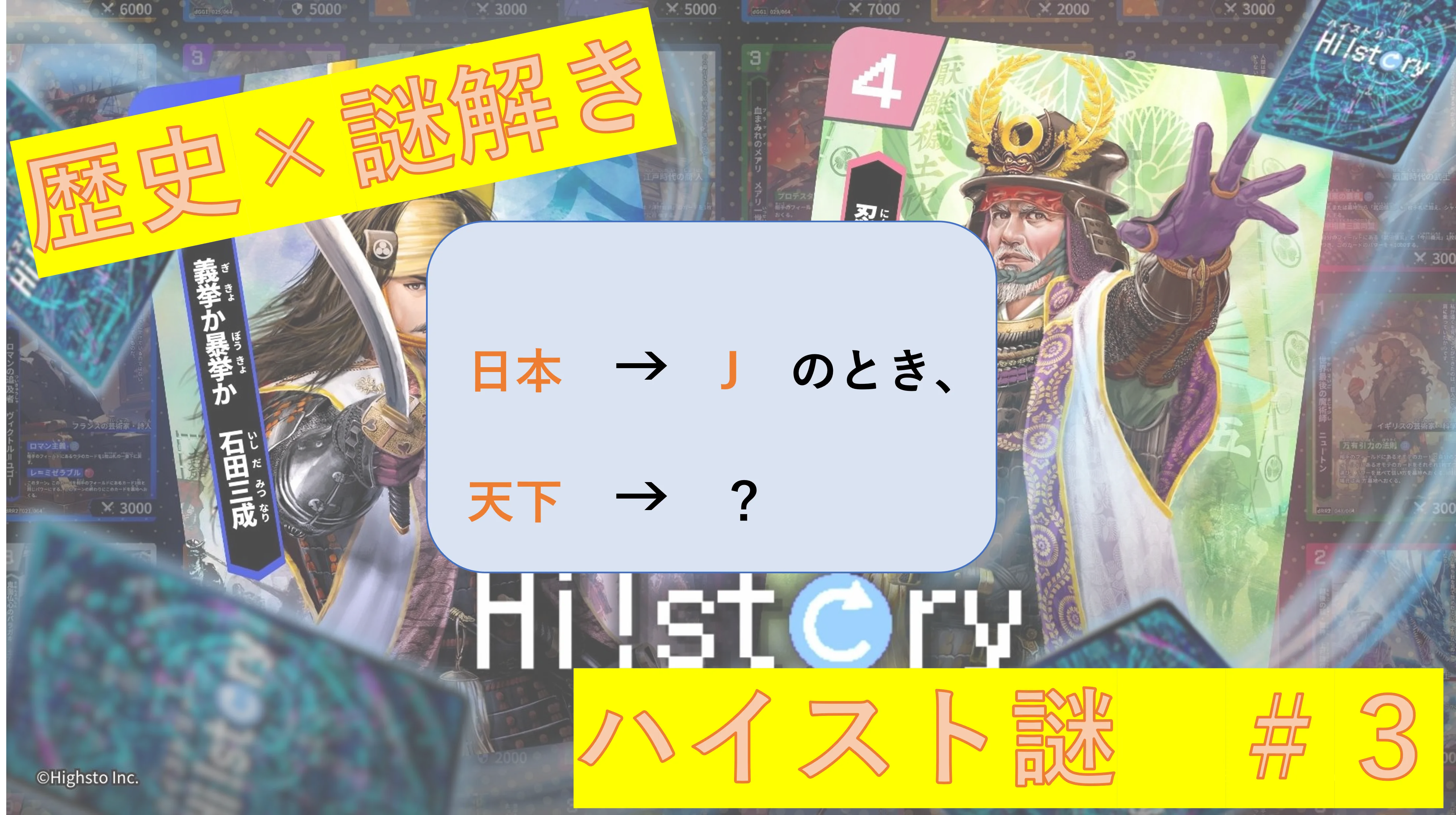
by かまだ
2025年01月16日

by Ropi
2025年01月09日

by むろ
2025年01月20日

by えんざん
2025年01月02日

by かまだ
2024年12月30日

by かまだ
2026年02月05日
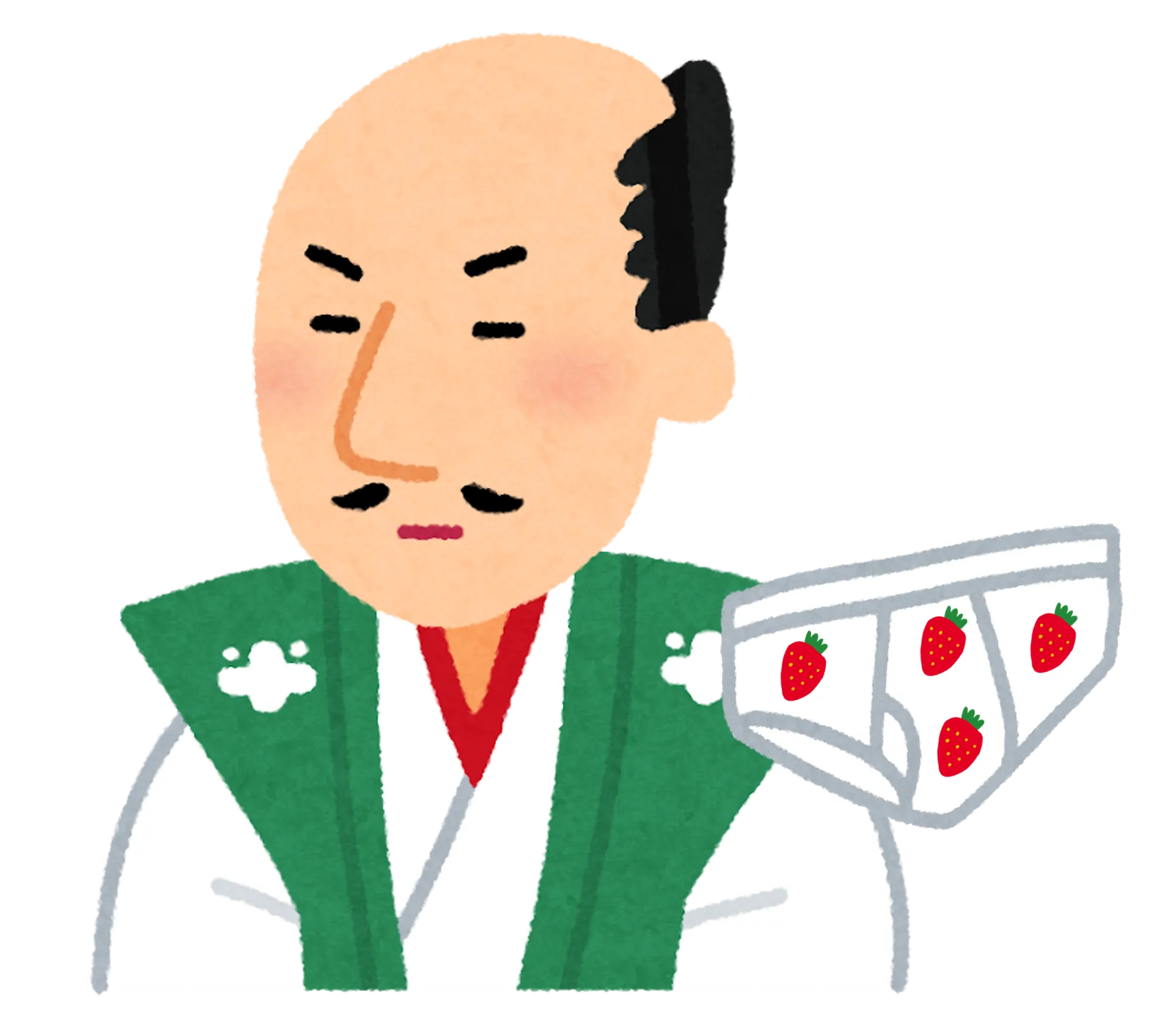
by かまだ
2026年02月02日

by ササノン制作班(ゆーき)
2026年01月29日

by むろ
2026年01月26日
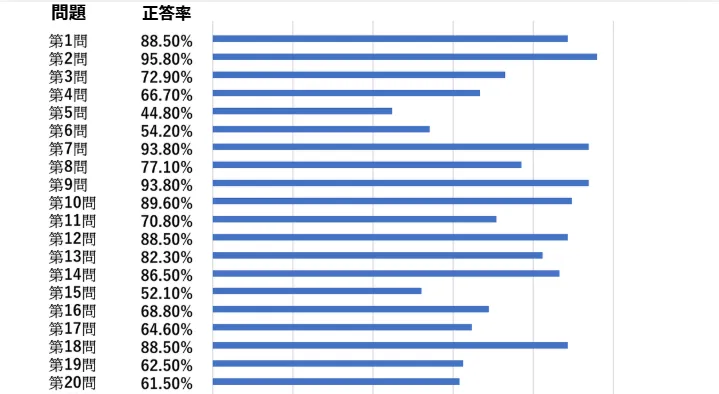
by かまだ
2026年01月22日