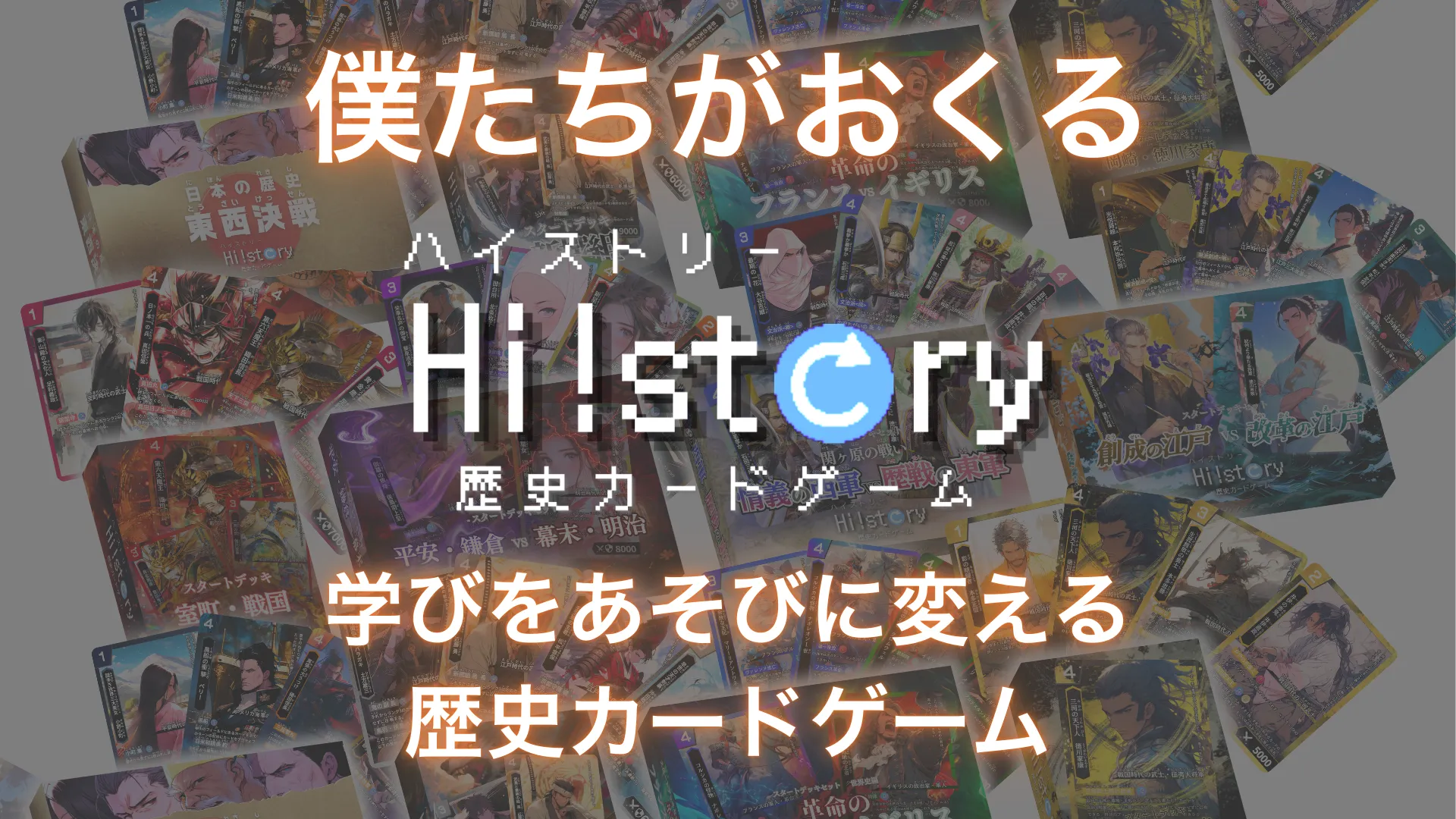「幸せ」ってなんだろう? ~歴史を振り返って考察してみた~
クイズを読み込み中…
Loading...

0 /10
合計 0 いいね
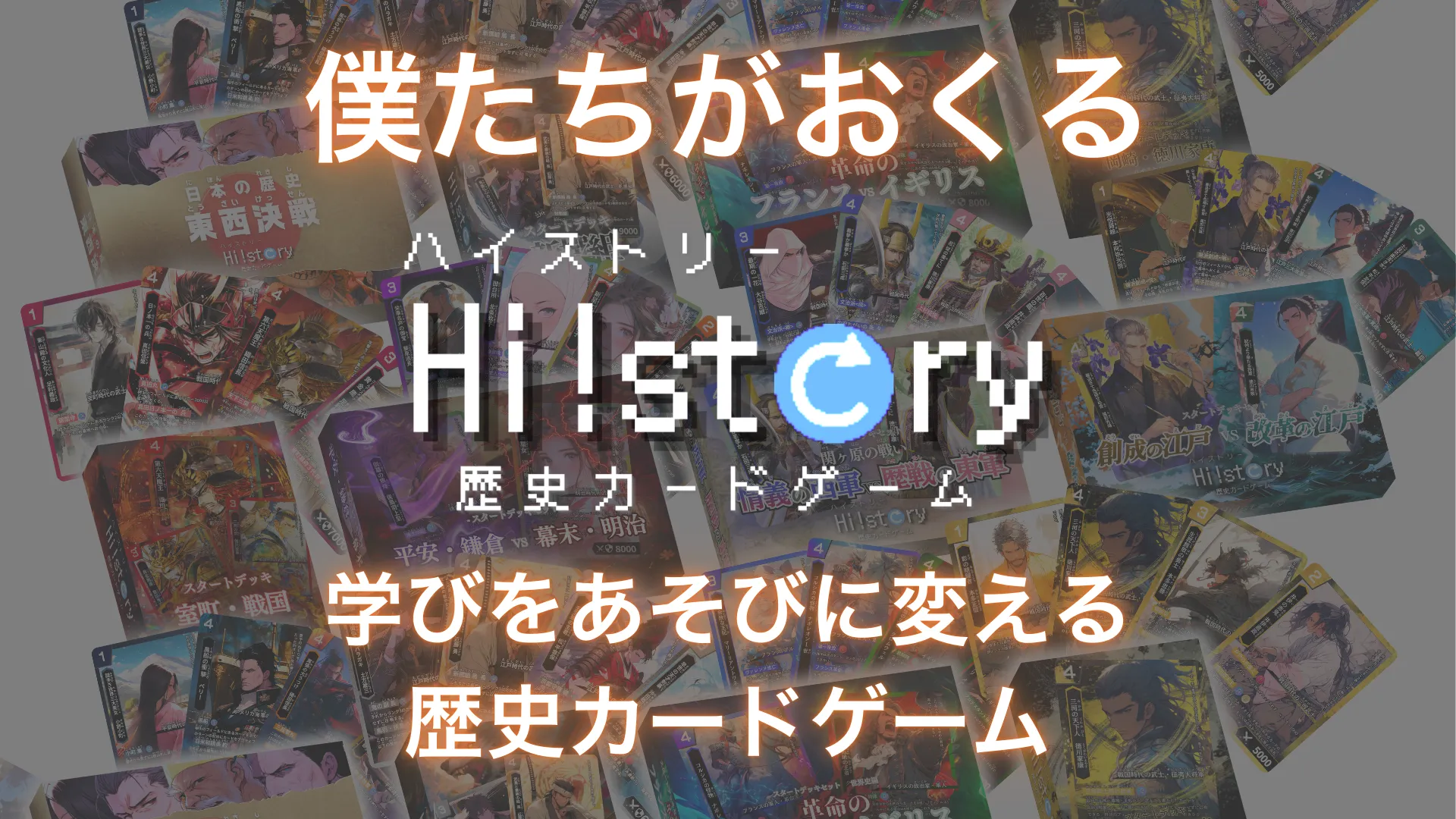


by Ropi
2025年08月11日
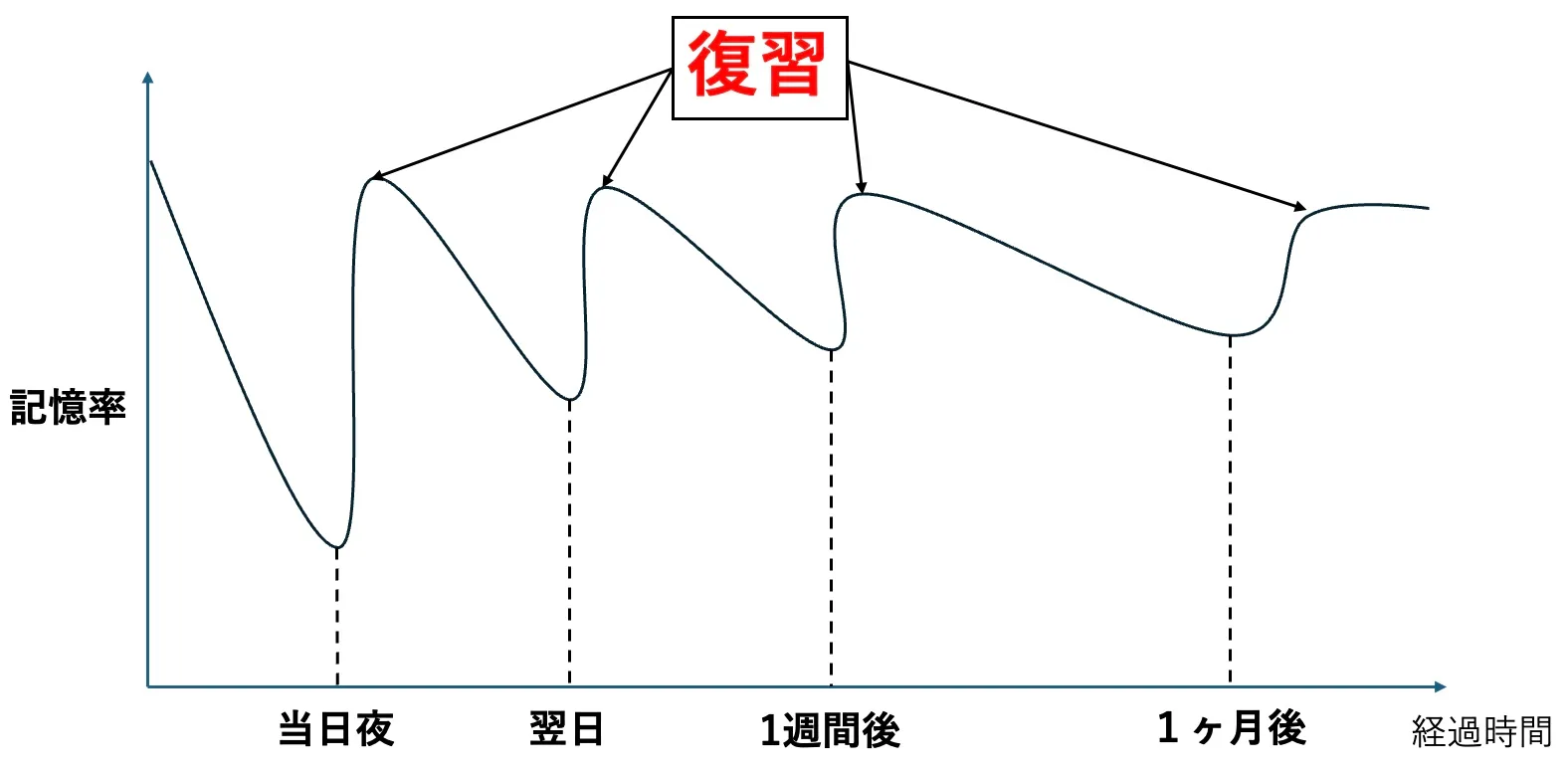
by むろ
2025年10月16日

by かまだ
2025年10月02日

by むろ
2025年08月18日

by むろ
2025年12月18日

by Ropi
2026年01月15日

by Ropi
2026年01月12日

by Ropi
2025年11月13日

by むろ
2025年07月17日

by Ropi
2025年08月11日

by むろ
2025年08月18日

by むろ
2025年08月07日

by Ropi
2025年06月23日

by かまだ
2026年02月05日
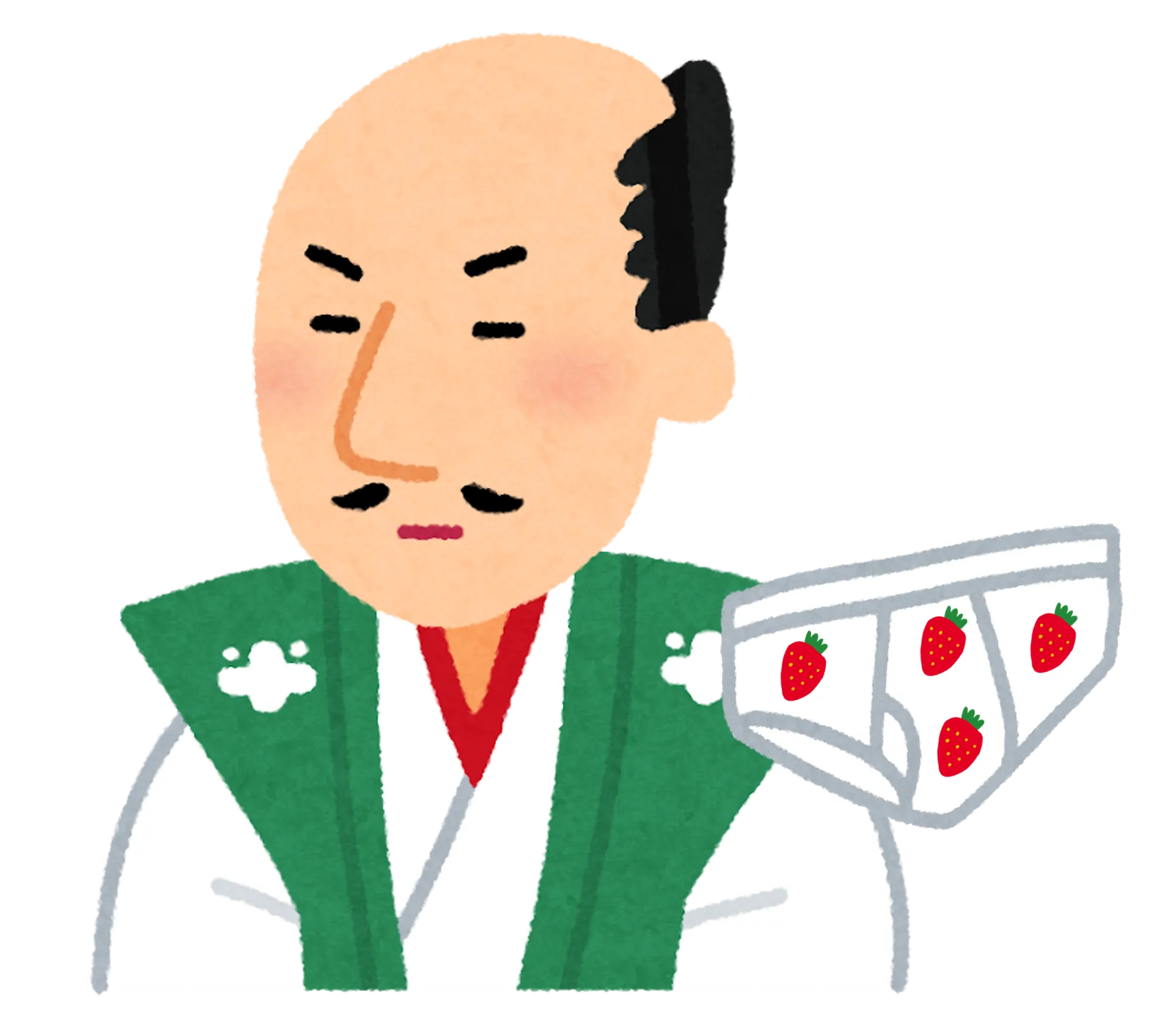
by かまだ
2026年02月02日

by ササノン制作班(ゆーき)
2026年01月29日

by むろ
2026年01月26日
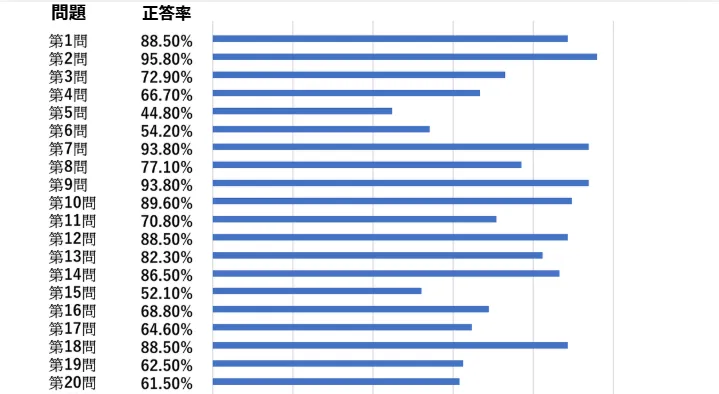
by かまだ
2026年01月22日