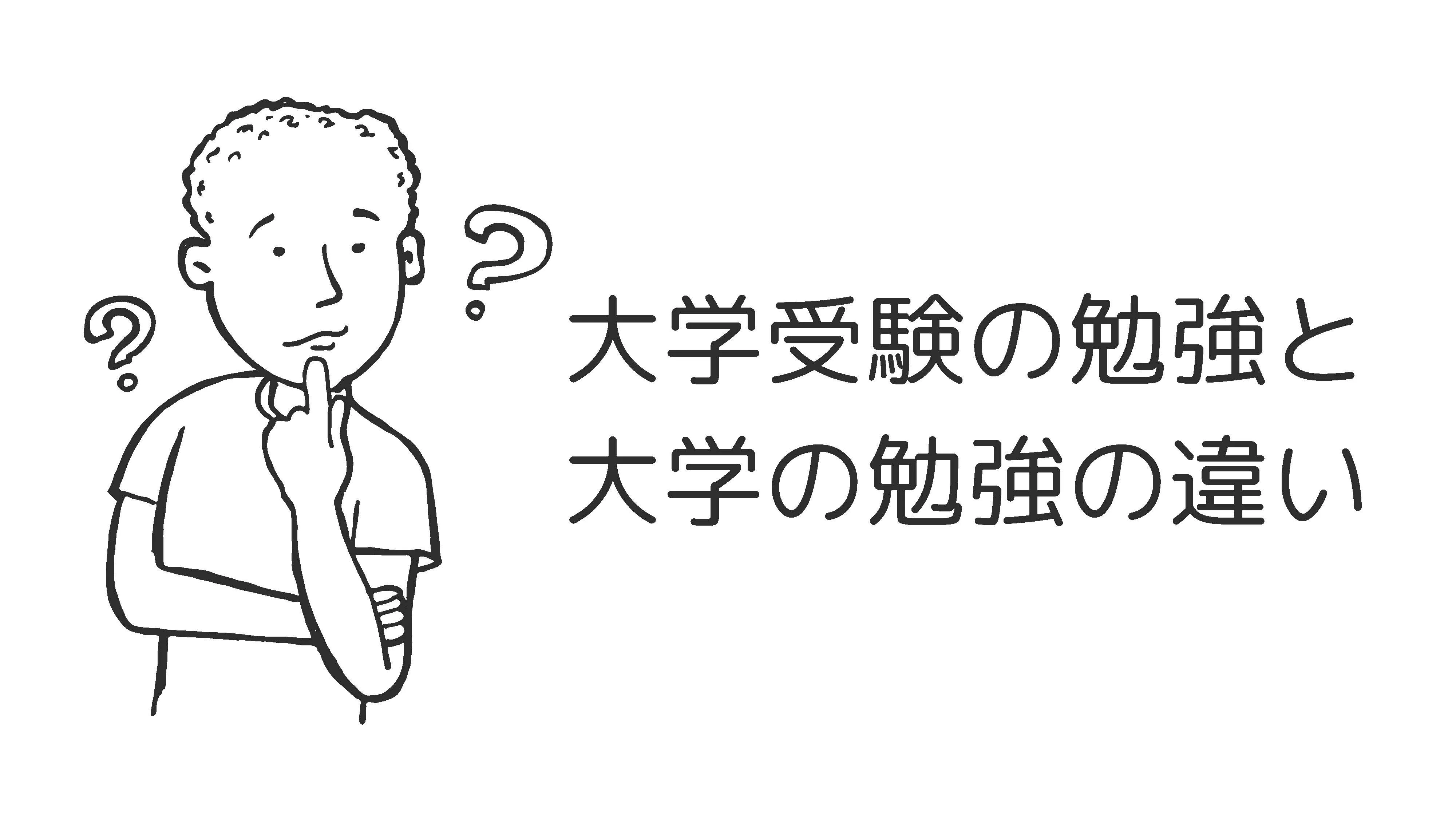
大学受験の勉強と大学の勉強の違い
クイズを読み込み中…
ハイスト勉強法記事シリーズ
シリーズ記事一覧Loading...

0 /10
合計 0 いいね
ライターに応募
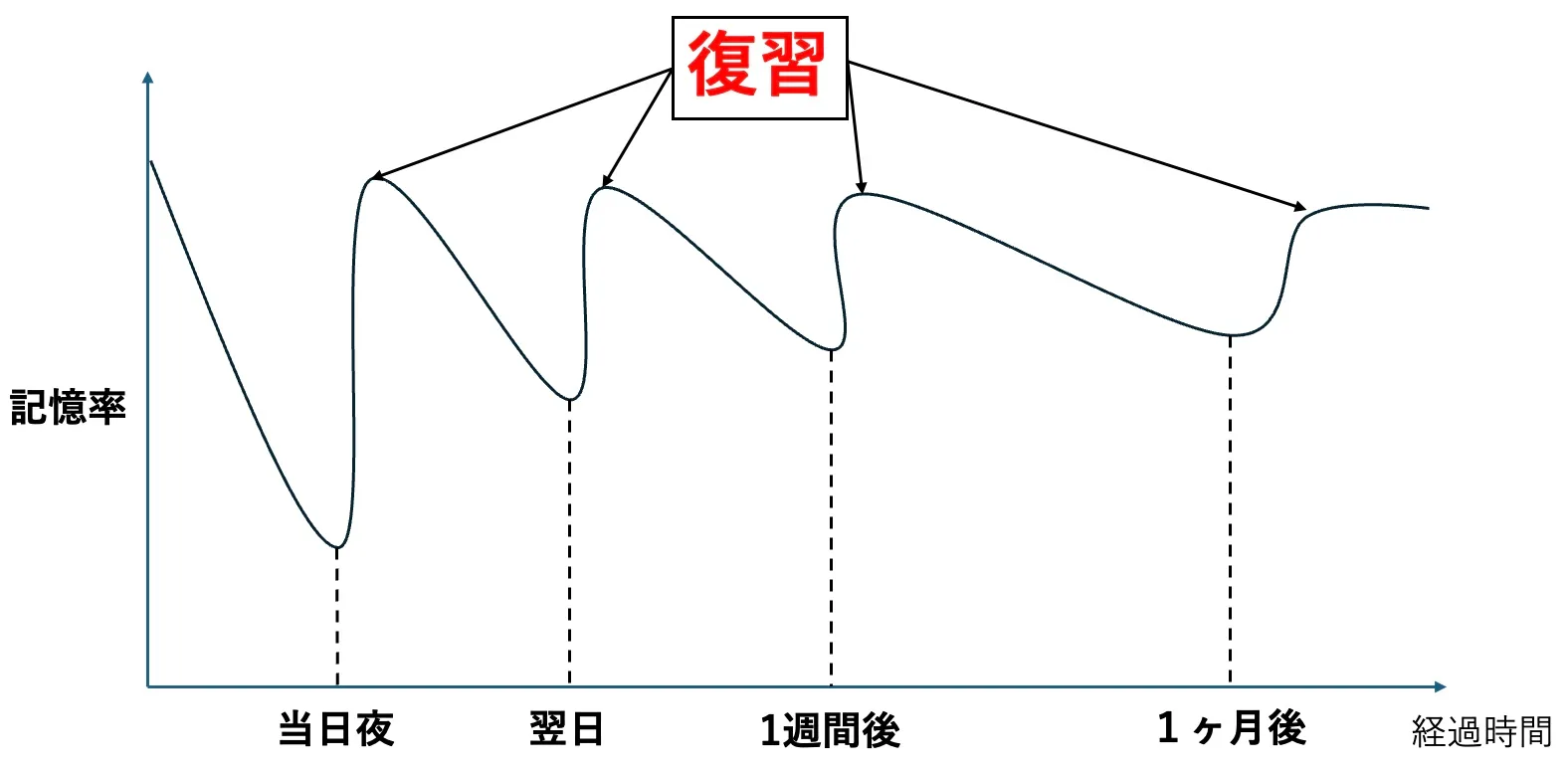
by むろ
2025年10月16日

by Ropi
2025年08月11日

by むろ
2025年08月18日

by かまだ
2025年10月02日

by むろ
2025年12月18日

by Ropi
2026年01月15日

by Ropi
2026年01月12日

by Ropi
2025年11月13日
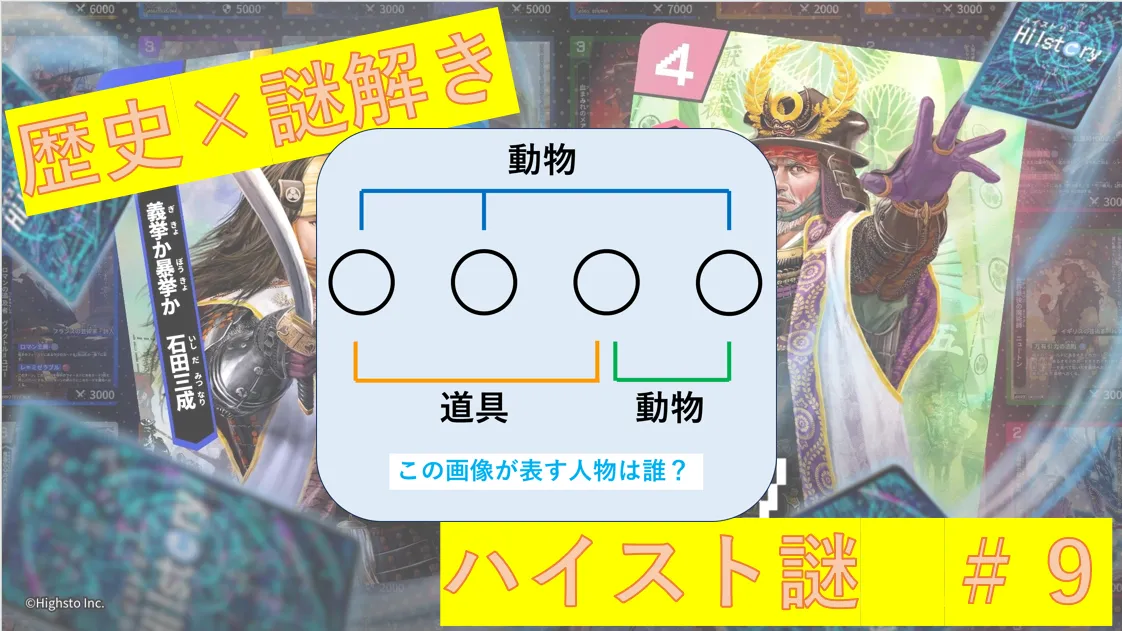
by かまだ
2025年03月27日
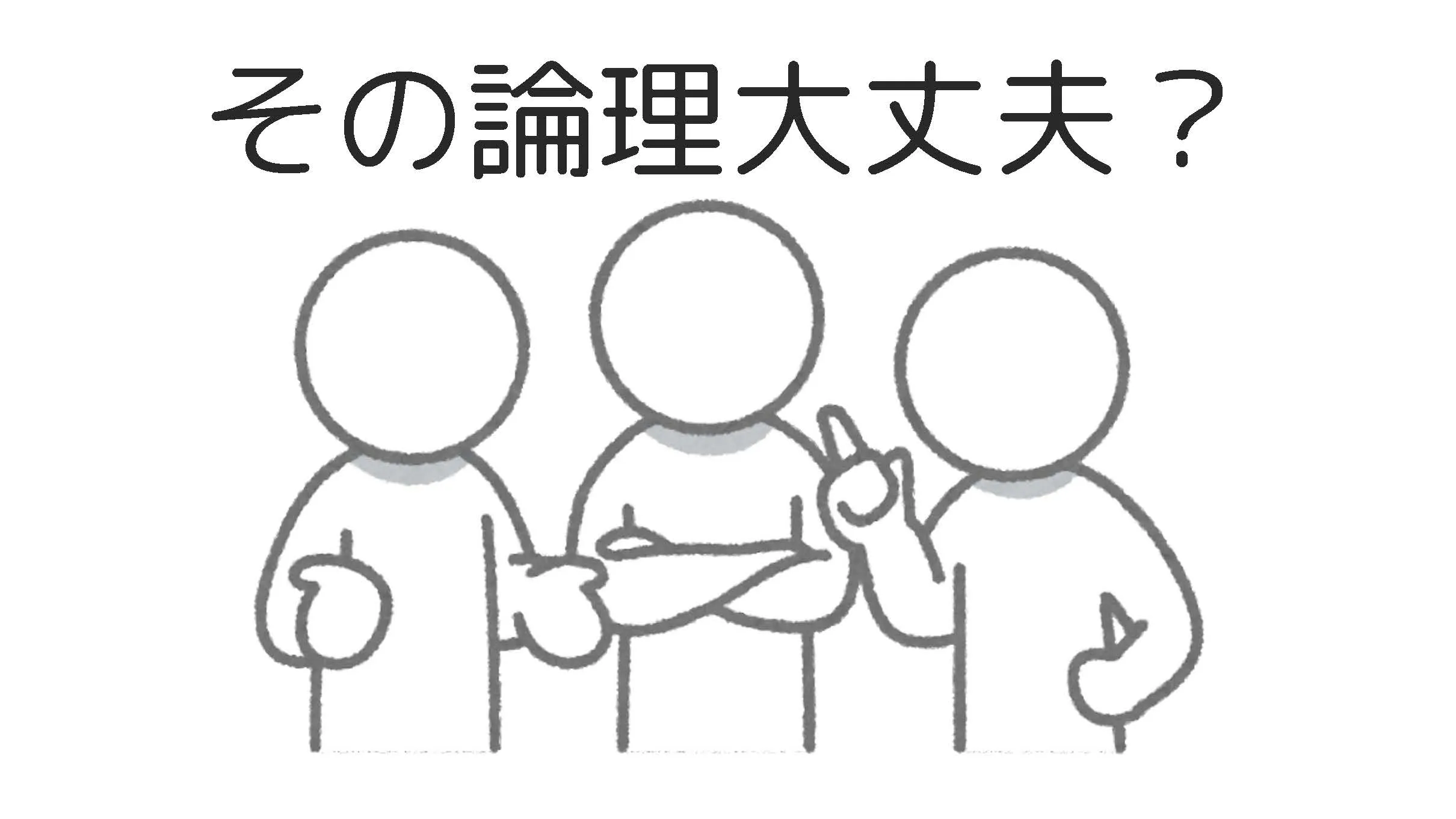
by Ropi
2025年03月31日

by かまだ
2025年03月20日

by ノーサイドくらはし
2025年03月17日
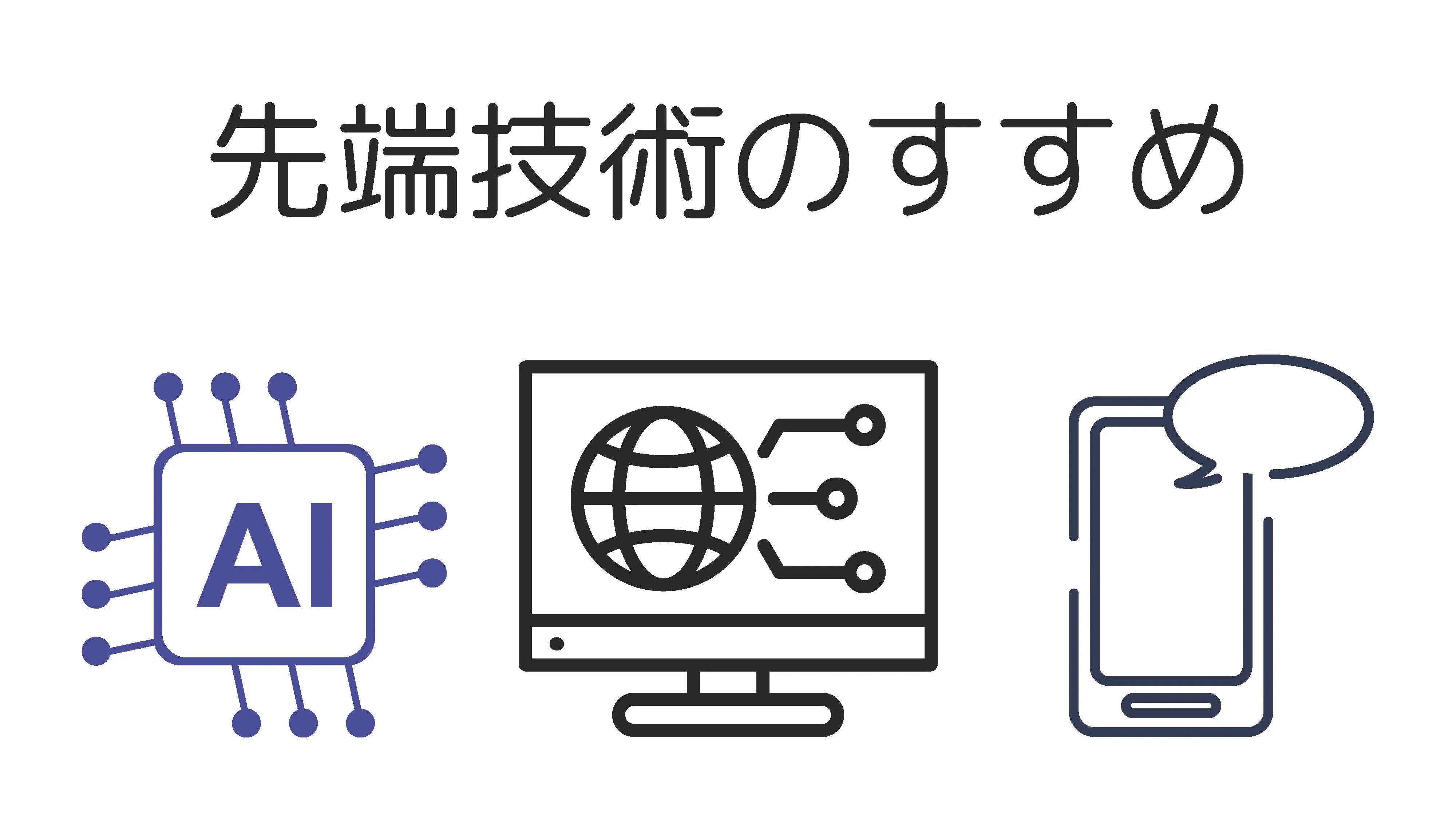
by Ropi
2025年04月07日